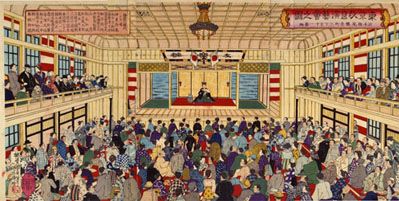特設
古今亭志ん生の本名は美濃部孝蔵といいました。美濃部家は徳川宗家の旗本でした。遠くは甲賀の出身だそうです。そう、甲賀忍者を先祖とする家だったのです。神君伊賀甲賀越えに随従したのだとか。ほら、「大河」でやってたアレですね。忍者と噺家。どこか似ていますね。人をけむに巻く、とかで。そこで、2023年9月21日、志ん生の没後五十年をしのんで、志ん生の人となりを、さまざまな観点から考察していきます。これぞ考察!
高田裕史
第一番 天敵三選
①円生 ②漬物 ③ナメクジ
①志ん生が、人間的にも芸風にもどうにも好きになれなかったのが、十歳下の円生だった。後年、両者が、時に知人に、または対談などで、かなり露骨に互いに辛辣な言葉を浴びせている。これは矢野誠一が指摘している通り、たたき上げでのし上がった志ん生と、御曹司(継父が五代目円生)でエリート意識が強かった円生では、ウマが合うはずもない。なまじ満洲(中国東北部)で食うや食わずの極限状況の共同生活をするうち、些細なことで衝突、なじり合いを繰り返し、それが戦後帰国してお互い大幹部になっても尾を曳いていたということだろう。※『志ん生のいる風景』(矢野誠一、文藝春秋)
②志ん生の漬物嫌いは、長女美濃部美津子の著書などでも紹介されているが、これはひとえに志ん生が生涯持っていた、自分は士族、それもれっきとした旗本の子だという自負と矜持によるものとみえる。「漬物(コウコ)は農民の食べ物」と麻生芳伸にも漏らし、若い頃から親しかった宇野信夫にも「士族自慢」をたびたびしていたという。ということは、①についてはじつはこんなこともいえよう。志ん生はすさまじいエリート意識で芸人出の円生を見下していたと。志ん生も円生も別なベクトルのエリート意識をひっさげていたわけ。矢野の見方は皮相で、真相はこんなところだろう。
③これは志ん生ファンには説明の要はない。五寸もあるのが「カカアの足に食いつき」「這った後の壁がピカピカに」「猛毒で猫が七転八倒」……よくまあ、食い殺されなかったものだ。
第二番 好物三選
①納豆 ②マグロブツ ③酒茶漬け 番外 氷水
①「お父さんは納豆が大好物でした。昔、納豆売りに失敗したとき、やんなるほど食べたでしょ。普通ならそれで嫌いになりそうなもんなのに、年とってっからも毎日食べてた。ほんとに好きだったんでしょうね。(中略)とにかく、納豆なしじゃいらんないってくらいでしたね」。1961年ごろ録音の、志ん生一家の朝の日常を生撮りしたドキュメンタリー(?)でも、妻のりんが「よく毎日ナット食べるね」と呆れている。※『三人噺 志ん生・馬生・志ん朝』(美濃部美津子、扶桑社)
②晩年の志ん生が贔屓にした文京区千駄木の居酒屋「酒蔵松風」の女将の証言。「(酒の)サカナはブツ専門でした。普通のおさしみはあがらないの。マグロが大のお好みでしたね」……。これは美津子の著書にもある。よほど好きだったと見え、1946~58年まで、アメリカによる23回もの核実験の影響で放射能汚染が問題となった「ビキニまぐろ」も、志ん生は値下がりしたのを幸い、モノともせずにパクついていたという。※『志ん生伝説』(野村盛秋、文芸社)
③弟子、古今亭円菊の証言。「てんぷらなんか食べにいっても、とにかく、キューッと一杯、冷やで飲んで、あともう一杯は、天ドンなら、どんぶりのなかへビャーッとかけて、”酒茶漬け”というか(略)酒でごはんを食べますからね。。うまいんだそうです」※『志ん生伝説』。
番外「氷水」 これは四代目三遊亭円楽の証言前座時分、楽屋では志ん生は「出来れば氷水という方。猫舌だったのか熱いお茶は好みませんでした」。※『円楽芸談しゃれ噺』(四代目三遊亭円楽、白夜書房)
第三番 迷言三選
①酒はウンコになる ②二円五十銭よこせ ③女、とっかえろ
①正確には「ウーン、ビールは小便になって出ちまうけれども」に続く。「すごい奥の深いことをおっしゃる方でございますね。並大抵の人じゃ言えないお言葉でございましてね。(笑)ずいぶんいろんなお話を伺ったんですが、これが一番わたくしの心に、強く強く残っている名言なんでございます(笑)」。亡き名優に敬意をこめて、断然これがトップ。ビールは水代わりで、夜中に弟子が「水持ってこい」と言われて本当に水を持っていくと「バカ野郎」と雷が落ちたそうな。※『小沢昭一的新宿末廣亭十夜・第二夜 志ん生師匠ロングインタビュー』(小沢昭一、講談社)
②「天敵」に関連して、六代目円生が後に対談で暴露。満洲時代のこと。奉天へ向かうため、新京(長春)のホテルを引き払うとき、一台しか来なかった人力車に志ん生一人だけ乗ったのに、後で円生に「五円取られたから二円五十銭よこせ」と割前を要求。「君一人しか乗らなかったじゃないか」「お前のカバンを乗っけてやった」。聴いていた一同は爆笑。こりゃ誰でも怒る。
③志ん生の若き日の飲む打つ買うのメチャクチャぶり、珍談なら、もうこれは甚語楼時分からパトロンだった坊野寿山の証言にかぎる。すさまじい話が多すぎるが、女に関してはとにかく手が早く、貪欲だったようだ。これもその一つで、ポン友だった当時の馬の助(のち馬生)に女郎屋で十銭出して、こう強要した。友達の相方でもおかまいなしに「強奪」しようという。さすがに「冗談じゃねえ。ワリ(寄席の給金)じゃねえや」と拒絶されたよし。
第四番 パトロン取り巻き三選
①坊野寿山(1900-88) ②小山観翁(1929-2015) ③宇野信夫(1904-91)
①若い頃からのパトロンにして、生涯の遊び仲間だった。当人が都合よく忘れている旧悪はすべて覚えていて、ほとんどこの人によって暴露され、貴重な記録として残されている。志ん生より十歳下にもかかわらず、日本橋の呉服屋の若旦那で金は湯水のごとく使い放題だから、噺家が食らいつくにはこれ以上ない。後年は「川柳家」として大をなす。志ん生も寿山の勧めであまりうまくない川柳をひねっている。
②知る人ぞ知る「昭和の大通人」。もとは電通のプロデューサーで、川尻清譚門下の歌舞伎研究家、特に歌舞伎座の初心者向きイヤホンガイドでも有名だが、もとより落語の方も生き字引。志ん生とこの人の結びつきは『対談落語芸談4・古今亭志ん生』(弘文出版)にくわしい。学生時代から始まり、就職後は電通制作の落語番組で志ん生を起用したことから公私ともに親交を深め、狷介な志ん生を巧みになだめすかして仕事の面倒を誰よりもよく見たことで、「小山亭が言うんじゃしょうがねえ」と晩年の志ん生が唯一「何でも言うことを聞く」といわれたほどの人。
③劇作家。昭和初期、六代目尾上菊五郎のために、数々の新作歌舞伎脚本を書き下ろしたことで有名。若い頃から落語にも造詣が深く、六代目円生とは特に親しかったが、志ん生とは柳家甚語楼時代、宇野がまだ学生だった昭和初期からの遊び仲間。埼玉・熊谷に本店を持つ染物店の若旦那だった。坊野ほどではないが、やはりパトロン的存在である。『昭和の名人名優』(宇野信夫、講談社)には、あまり知られていない甚語楼時代の貴重なエピソードが多数収まる。
第五番 コレクション道楽三選
①たばこ入れ ②和時計 ③金魚
志ん生の古道具、骨董趣味は家族や門弟などによってよく語られるが、もちろん戦後、極貧とおさらばして功成り名遂げ、趣味に金と余暇を使えるようになった晩年の楽しみだったろう。
①は文楽と競争してコレクションしたという※『志ん生伝説』。「オレが文楽に教えたんだ」と威張っていたとか。これに関しては坊野寿山の回想も。「私しゃ死んでも離しませんから」と志ん生に高価なタバコ入れをねだられ、しかたなく中身ごとやると、五、六日して柳枝(八代目)が来たら、その煙草入れでうまそうにスパスパ。志ん生から五円で買ったらしい。「あの野郎、モートル(=博打)で負けて、五円なんかで売っちまったんだ」
②これも『志ん生伝説』による。谷中の時計店氏の回想。弟子(おそらく円菊)におぶわれて来店したというから最晩年だろう。一度買っても気に入らないと、何度でもまた買い直しにきたくらい凝っていたとか。もっぱら白の和時計で、飽きると片っ端から人にやってしまったようだ。
③古道具や骨董同様、ペットも欲しいとなったら片っ端から衝動買いし、片っ端から飽きてまた別の動物を飼う。長女美津子の証言によると鳥ではインコやカナリア、ウグイス。犬もしょっちゅう取り換える。その中でもっとも長続きしたのが「金魚金魚ミイ金魚」。自宅裏庭の池で泳がせ、金魚釣りをして無邪気に喜んでいたという。
第六番 志ん生の新作落語三選
①一万円貰ったら 「講談倶楽部」1939年5月増刊号所載
②隣組の猫 「富士」1940年10月号所載
③強盗屋 「キング」1937年4月増刊号所載
新作を中心にした速記を集成した『昭和戦前傑作落語全集』には志ん生のものは計21題が掲載されているが、矢野誠一によると、志ん馬改名(1934年7月)の頃から自作と称して新作の速記をよく出版社に持ち込んでいたらしい。ここにラインナップした3題はそのうちまあまあおもしろいと勝手に判断して順に並べたもの。いずれもどうやら自作らしい。
①は志ん生襲名後のもの。 古典の「気養い帳」風に、長屋で大家が景気づけに「仮に1万円(現代だと数百万)貰ったら何に使うかと次々に聞く。例によって頓珍漢な解答の後、最後に「双葉山贔屓だから、国技館で祝儀に双葉にやっちまう」「全部?」「いえ、九千九百九十九円九十三銭」「あとの七銭は?」「帰りの電車賃にとっとく」というセコいもの。
②の噺の眼目は不細工なかみさんをグチるくすぐりで、それも後世「火焔太鼓」などに使ったものよりずっと過激で、なぜか戦後はほとんど消えた幻の逸品揃い。「唇が薄いというからてめえを貰ったんだ。薄けりゃベラベラしゃべるから、借金の言い訳になると思ってよ」「あの顔色をごらんよ。頬骨が出て眼肉がこけて、まるで患ってる鰻だよ」と亭主が言えば女房も「(貧乏暮らしで)人の肉を盗っちまいやがって、泥棒っ」と応酬するなど、この夫婦げんかだけでも二位の価値は十分。
③はまだ七代目馬生時代で、実は気の弱い旦那が、細君に自分は柔道三段だから強盗なんぞ怖くないと見栄を張り、それを証するため、これも気の弱いルンペンに、5円で狂言の強盗役を頼むが……というライトコメディー。オチも含め、なかなかよくできている。
第七番 志ん生作の川柳三選
①羊羹の匂いをかいで猫ぶたれ
②のみの子が親のかたきと爪を見る
③捨てるカツ助かる犬が待っている
志ん生が「旦那」の坊野寿山の勧めで、生涯かなりの数の川柳をものしたことは「パトロン」の項でも触れたが、あくまで「川柳」であって文人気取りの俳句でなかったことがこの人らしい。割にファンの間で有名なものには、『びんぼう自慢』の巻末にある「エビスさま鯛を取られて夜逃げをし」「松茸を売る手にとまる赤とんぼ」「豆腐屋の持つ庖丁はこわくない」「雨だれに首を縮める裏長屋」など、ペーソスを効かせたなかなか洒脱なものも多い。ここではあえて、「コレクション道楽」の項でも紹介したように当人が動物好きであったことも考え、動物で三句を選んでみた。矢野誠一が一度直接当人に尋ねたら「別に」とそっけなかったそうだし、せっかく飼っても例のズボラと気まぐれですぐ飽き、ペットもとっかえひっかえではあったようだが、これは江戸っ子特有の照れやシャイな気質の表出と見る。志ん生は得意ネタ、マクラ、小噺でも動物を擬人化したものがうまく、そこには、弱い虐げられた者の怒りや悲しみを動物に託した、敗残の江戸人の生き残りの精一杯の反骨心があるといえる。その意味で、飢えてぶたれた猫も、親をつぶされたノミの子も、捨てられたカツに飛びつく野良公も、すべて若き日の餓えた美濃部孝蔵そのものの分身だったのだろう。
第八番 志ん生の恩人三選
①美濃部りん
②初代柳家三語楼
③三代目小金井芦州
番外 上野鈴本・島村支配人
①はもう、これは誰も文句はないところ。ミセス・ミノベなくして美濃部孝蔵も五代目古今亭志ん生もなく、それどころか噺家を廃業したまま、陋巷に野垂れ死にしていたかもしれない。あらゆる資料のあらゆる関係者でこの老夫人を褒めない者はいない。「賢夫人」「『あわびのし』のような夫婦」「器用で裁縫上手で、自分の内職一本で夫と子供たちを養った」「普通の人間なら、たとえ大正の昔でもとっくに別れている」「子供の頃からの苦労人で、極貧生活なのに、困っている人間を見ると有り金をやってしまう」……。こうなるともう菩薩、聖母マリアそのもの。にもかかわらず背信亭主は、祝言の夜から仲間と居続けでチョーマイ(女郎買い)。ヒモ同然に同棲していた女と、結婚後もしばらく縁が切れず(二人の子が後の某大女優という説あり)、大看板になっても向島の芸者のところに回数券付きで通っていた(円菊談)……。菩薩の顔も三度までで、「さしものお袋がもう別れようと思ったことは二度三度じゃなかった」(長男馬生談)。にもかかわらず、とうとう50年間添い遂げてしまう。こんなかみさん、絶滅種どころか、もはや日本のどこにも存在しないだろう。
②③はそれぞれ、五人目(最後)とその前の師匠。志ん生自身は、「師匠」と仰ぐのは、終生最初の師匠と頑なに言い続けた名人・四代目橘家円喬だけで、実際の最初の師匠・二代目三遊亭小円朝を含め、他の師匠には尊敬もなにもなかった。ただ、三語楼と芦州は、それぞれ芸の上では大恩人だった。
第九番 志ん生への寸評三選
①志ん生は色彩、文楽は写真(小絲源太郎)
②文楽は古典音楽、志ん生はジャズ(徳川夢声)
③オヤジ自体が落語(古今亭志ん朝)
①は日本芸術院会員で文化勲章受章者の洋画家によるもので、この言葉だけで志ん生のみを「芸術家」と遇しているようなもの。黒門町ファンには大いに反発を招くだろうが、古い世代の画家(1887年生、志ん生より三歳上)にとって、写真はただ「機械的な現実もどき」の大量生産に過ぎないとするなら、いつも固定して動かない文楽の芸をこう例えたとしてもおかしくはない。
②の夢声は対談相手でもあり、個人的にも親交があったから、古今亭贔屓なのには違いないが、①に比べ、より公正でわかりやすい評。つまりは厳格な格式・様式と自由奔放な変奏・くずしという、ごく一般的な両者の芸への感想を西洋音楽に例えたセンス。ただ、若き日の志ん生がどちらかというとオーソドックスな正統派の芸を志向し、結局それでは売れなくて、やむを得ず三語楼流の破格の芸に走った事実は、同世代の夢声老(1894年生)なら当然知っていたはずだが。
③は円朝にはなれて志ん生にはなれなかった次男坊の、シンプルかつすべてを包含した嘆息。
第十番 あだ名三選
①人差し指
②貧乏神
③オケラのコーちゃん
①複数の出典があるが、代表的なものでは、甚語楼時分の志ん生のパトロンの一人で、遊び友達だった宇野信夫が自著『昭和の名人名優』ほかで暴露している。バクチ狂いだが始終負けてはスッテンテン。どうにもならなくなると「ここへこれだけ(タネ銭を貸せ)」と人差し指を出す。ということはたぶん一円。もちろん誰も相手にしない。単に「指」とも。
②四代目柳家小さん。「甚語楼に渋団扇を持たせたら貧乏神」と評した、同業者で同世代ならではの辛辣な命名。つまりは昭和初年の志ん生は、なりがほとんど物乞い同然であるばかりか、芸もまた垢じみてて貧乏臭かったということでもある。
③三味線漫談、都家かつ江の証言。志ん生三回忌の1975年、『志ん生伝説』の著者野村盛秋に語った追想コメントで、例えば花札でオケラ(麻雀でいうハコテン)になると、例によって「貸してくれ」。で、自称二円五十銭の高級時計をカタに置いていくが、案の定受け出しに来ない。結局、始終時計屋へ直しにいかなければならない、二束三文のオンボロ時計だということがばれ、ねじ込むと「だからさー、キミがあの時計を持ってネ、時計屋へ養子に入りゃいいんだよ」……。これが大看板の志ん生を継いだ後だから、あきれ果てる。というか、志ん生というパターン化に成功したわけ。
第十一番 芸のポリシー三選
①教えた噺はやらない
②汚い噺はやらない
③言葉が、正宗の名刀であれ
①これはどの門弟後輩に対しても共通したポリシーで(真打ちに限るが)、噺は財産なので、きちんと教えたネタは譲ってやったも同じだから、原則としてもう自分では封印する。これは江戸っ子の美学であると同時に、その教えた相手がどんなに汗をかいて熱演しても、到底志ん生には及ぶべくもないから、それによって自信を失わせることを避けた思いやりでもあるだろう。
②は、どんなに薄汚れた世界を演じても、美学に反する噺だけはやらない、というサムライの末裔のプライドか。例えばどんなに勧められても、弱い立場の女郎をよってたかって酷い目に遭わせる「突き落とし」だけは頑として演じなかった。また、バレばなしはやっても、「汲み立て」「禁酒番屋」ほかの、文字通りのスカトロネタは演じなかった。志ん生にとっての「汚い噺」というのは、その両方の意味を兼ねるのだろう。
③はえらく大きく出た言い方に聞こえるが、内弟子時代から私生活にも密着し、せがれ同然にかわいがられた円菊の語り残し。長男の馬生に稽古をつけているそばで聞いていたことで、言葉のメリハリには厳しかったということ。細かい表現などは意味が通じればいいが、名刀のようにコトバが切れなくっちゃいけない、間違っても二度同じことを言うな、とも。なるほど、フニャクニャムニャムニャ言っているようでも、よく聞けば志ん生の「セリフ」ははっきりわかる。メリハリのよさ、センテンスをスッパリと短く切るさわやかさは、即妙のギャグを活かすもっとも重要なポイントだったわけだ。
第十二番 同い年生まれ三選
①ドワイト・アイゼンハウアー
②シャルル・ド・ゴール
③教育勅語(本人推薦)
番外 花王石鹸 帝国ホテル、凌雲閣、国会議事堂、電気椅子(米)
明治23年(1890)戊五黄寅生まれの赤ん坊は、統計資料によれば、日本だけで男女合わせて約119万人。世界中を見渡せば、おそらくその二十倍はいただろう。どの年でも同じだが、その中で、少なくとも人名事典に名を残すほどになった者も山ほどいる。もっとも、「偉人」の領域になるとかなり絞られるが、それをいちいちあげていればキリがない。五代目古今亭志ん生こと故美濃部孝蔵氏が偉人かどうかは評価がわかれるだろうが、少なくとも「芸術家」の分野に限れば、まあまあ世界トップ100には入れたい気がする。そこで①と②、現代史をひもとけば必ず出てくる世界的な政治家(将軍→大統領)ながら、美濃部孝蔵との共通点は……見事にまったくない。むしろ、同じ年に大小便垂れ流しながら生まれてから、70年も経過して、よくもまあ、これほど隔絶した人生をたどるものと、その究極の例としてだけあげておいた。いや、本当は③をトップに据えたいくらいで、これはご当人が『びんぼう自慢』で「教育勅語が降下になったのが、その年(明治23年)の10月だから、あたしのほうが教育勅語より少うし兄貴てえことになる」と胸を張っている。なるほど、志ん生流の四次元的発想では、別に「同い年」といったところで人間に限定しなければならないということはないはず。ところがあいにく、日本では明治23年という年、珍しく天下泰平極まる年で、主なできごととしては教育勅語のほかは、せいぜいが2月- 金鵄勲章制定だの、4月-内国勧業博覧会開催だの、その他、第一回衆議院議員総選挙、花王石鹸新発売、凌雲閣、帝国ホテル開業と、あまり歴史に残るイベントはない。そこでどうせ中途半端なら、志ん生も明治の子、尋常小学校の頃は「大臣・大将」が理想像だったろうから、いっそ大統領二人の同年生の方が喜ぶだろうと愚考した次第。番外では人間以外の方々もいくつかご紹介しておいた。
第十三番 冥途の道連れ三選
①七世芳村伊十郎-長唄唄方、9月20日没、享年72
②二十四代木村庄之助-大相撲立行司、9月19日没、享年72
③ J・R・トールキン-英、作家・詩人、9月2日没、享年81
残念ながら、少なくとも人名事典に名を残すほどの著名人では、志ん生師匠と同日(9月21日)に三途の川を渡った人は見当たらない。師匠より一日早く旅立った①の7世伊十郎は不世出の名人。人間国宝の肩書もあってトップに据えた。②とした24代庄之助は、柏鵬時代を裁いた名物立行司。「山伏庄之助」とも。③のトールキンは、文学の最高峰『指輪物語』の著者。サルバドール・アジェンデ(チリ大統領、9.11)、グスタフ六世(スウェーデン国王、9.15)、パブロ・ネルーダ(チリの詩人、9.23)なども。これらの人々と志ん生の接点は一切なし。強いて言えば共通点は「男」というだけだが、そういえば同行者の中には、残念ながら老いて逝った元女優何人かを除けば、妙齢のご婦人は見当たらなかった。肝心の同業者だが、この1973年には、同世代でただ一人、最初の師匠・三遊亭小円朝の長男、三代目小円朝があの世へ行っている。小円朝は二か月早く7月11日没(享年80)。若き日、志ん生が「ねずみの殿様」とあだ名を付けた人で、この人は二歳年下でもそこは「師匠のお坊ちゃん」で、なんとなく煙たい存在のまま終生あまり仲はよくなかったようだから、いっしょに道中したい相手ではなかっただろう。
第十四番 志ん生の弟子三選
①初代金原亭馬の助
②二代目古今亭円菊
③八代目古今亭志ん馬
志ん生が満州から帰国後、弟弟子(三語楼門下)から志ん生門に移った志ん太(のち二代目甚語楼)、同じく三寿(のち志ん好)を別格として、志ん生直門の弟子は長男の四代目むかし家今松(のち十代目金原亭馬生)を筆頭に、最後の志ん五まで12人。そのうち、早く廃業した者、五代目古今亭今輔門下に移籍した志ん治(のち鶯春亭梅橋で真打、早世)を除いて、真打になった者は8人。順に馬生、初代金原亭馬の助、八代目志ん馬、二代目円菊、三代目吉原朝馬、三代目志ん朝、初代志ん駒、初代志ん五。このうち、志ん生の実子だった馬生、志ん朝を別格とし、残り5人から3人をピックアップした。この選択はあくまでランダムで、人気や芸の評価からの順位付けではない。なお、2018年1月18日の志ん駒の死去を最後に、この8人はすべて故人となった。悲劇的にも、享年で師匠を超えたのは円菊ただ一人で、没年齢は順に馬生54、馬の助47、志ん馬59、朝馬47、志ん朝63、円菊84、志ん駒81、志ん五61。80歳を超えた2人を除いて、早世した弟子が多いのは、赤貧に鍛え上げられ、重い脳出血から奇跡的によみがえって83歳まで酒を飲み続け、なお芸への執念を燃やし続けた明治男の強烈なエネルギーに、どいつもこいつもみな生命力を吸い取られたためかとさえ思える。