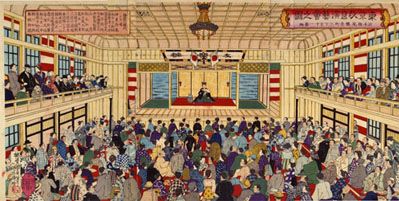成城石井.com ことば 演目 千字寄席 円朝作品
成城石井.com ことば 演目 千字寄席 円朝作品
尾崎秀樹(1928-99)。
尾崎秀実(1901-44)の実弟です。こちらはゾルゲ事件で帰らぬ人となった朝日新聞のエリート記者。今では歴史上の人物でしかありません。
弟の秀樹はといえば、「国賊の家族」として冷遇されつつ、台北帝国大学の医学専門部を中退。先の大戦後も苦労は続き、大衆文学の評論家として名を馳せるようになりました。チャンバラ小説と言えば尾崎秀樹がダントツでしたが、いまは亡き人、もう忘れ去られた存在です。
ゾルゲ事件では、尾崎秀樹は自著『生きているユダ』(八雲書店、1959年)で、伊藤律(1913-89)を事件の「ユダ」として糾弾しました。しかしその後、さまざまな新研究の結果、「伊藤=ユダ」説がほぼ覆されています。そんなこともあってか、尾崎秀樹が語られる場面も少なくなっているのでしょう。
日本では、文芸評論家という立ち位置は、小説家とは異なります。生きている間はすさまじく席巻し影響を及ぼすのですが、死んでしまうとそれっきり。他人の褌で相撲を取る風情、文壇のダニみたいな気配が敬遠されるのでしょうか。「うるさい奴が消えた」くらいのもので、没後は顧みられることがあまりありません。
河上徹太郎(1902-80)も、亀井勝一郎(1907-66)も、平野謙(平野朗、1907-78)も、十返肇(十返一、1914-63)も、保昌正夫(1925-2002)も、浅見淵(1899-1973)も、あるいは荻昌弘(1925-88)も、はたまた淀川長治(1909-98)でさえも例外ではなかったかもしれません。
例外は小林秀雄(1902-83)でしょうか。小林の書いたものはクリティークとして残されているように、私には映るのです。
それはともかく。
尾崎秀樹の仕事はチャンバラ評論ばかりかと思っていましたら、初期の頃には落語、それも円朝について記した作品があったのです。
「三遊亭円朝」という、一冊の刊行物にするにはちょいと寸足らずではありますが、薄っぺらな書きなぐった雑文とは異なる味わい、重厚で濃密で、しかも、円朝と仏教とのかかわりについて言及しているのは、おそらく、ほかには関山和夫(1929-2013)くらいかもしれません。
その中で、円朝より少し下った世代は円朝をどう見ていたのか、というくだりがありました。三代目柳家小さん(豊島銀之助、1857-1930)の円朝観を、小さんの『明治の落語』から引用している箇所を見つけました。
たいへんおもしろい内容なので、孫引きで載せさせていただきます。
「円朝は狂言作者を抱えて飼い殺しにしていた。芸は拙いし採る処はないが、作者がついていて常に新しいものを出した。一口に云えば山勘で興行師のような処がありました。年に春秋二回、十五日間位しかやらなくて高いお金をとっていたが、芸は拙い人でした。そこへいったら燕枝は円朝とは訳が違う。燕枝は人物が出来て居た。伯猿という人も、大した評判でしたが、講釈のまずさ加減というものは、無茶苦茶でまるで素人のようなものでした。伯猿と円朝は何故そんなに評判になったかというと、それは番付によい処に出すものですから、あんなになったのです。……(略)話が下手でも、狂言作者が附いていたので、次から次へと新しく行った。それだけのもので円朝は頭の悪い人でした」
以上が三代目小さんの弁。
いやあ、ひどい言いようです。でも、見ようによってはこんなところも円朝にはあったのかもしれませんね。
燕枝とは初代談洲楼燕枝(長島傳次、1837-1900)のこと。柳派における円朝のような存在です。小さんの立場からすれば自陣の人です。
円朝が逝った明治33年(1900)、燕枝も半年ほど早めに没しました。
燕枝も新作をものしています。
円朝と違って自ら書き残したものが多いため、今後、格好の研究対象として発掘されていってもよいのですが、円朝研究ほどの成果は上がっていません。
伯猿とは二代目松林伯円(手島達弥→若林義行→若林駒次郎、1834-1905)のこと。
当時の講談界の親分です。
明治政府からは、円朝と並んで「教導職」に任ぜられました。まあ、円朝と同列視される巨頭です。
「狂言作者を抱えて」のくだり、これは尾崎も触れていますが、仮名垣魯文(野崎文蔵、1829-94)、条野採菊(条野伝平、1832-1902)、三代目瀬川如皐(六三郎、1806-81)、梅素亭玄魚(宮城喜三郎、1817-80)、河竹黙阿弥(吉村芳三郎、1816-93)などとのつきあいを皮肉っているのでしょう。
この方々は、幕末に盛り上がった「粋興連」と称する同好の仲間でした。
条野採菊は、江戸期には山々亭有人という名の戯作者で、明治期には「警察新聞」を買い取って「やまと新聞」を創刊した新聞経営者に。鏑木清方(条野健一、1878-1972)の実父でもあります。
その変わり身ぶりは円朝にもいえることでしょう。
円朝は、江戸期には道具噺で歌舞伎もどきのにぎやかな芸風でしたが、明治5年(1872)には道具を弟子に譲り、わが身は扇子一本の枯れた素噺に変身したのですから。
三代目小さんと言えば、夏目漱石(夏目金之助、1867-1916)が「三四郎」などで絶賛した希代の話芸の名人でした。尾崎の言葉を借りれば、小さんとはこんな具合です。
三代目小さんは、頭の方はお留守だが腕はいい「与太郎」の登場する「大工調」とか、「笠碁」などをやらすと絶品で鈍重で邪気のない性格が、そのまま作中人物の性格になったといわれたはなしかだった。それだけに、才人で時代を見抜く眼のある円朝の動きは、ムシズが走るくらい嫌だったらしい。
「頭の方はお留守」なのは与太郎であって、小さんではありません。 誤読しそうです。日本語はややこしいです。
ここまで来たなら、ついでに、二派の違いを四代目柳家小さん(大野菊松、1888-1947)からの引用でちょこっと。これも尾崎論文からの孫引きですが、まあ、お読みください。
柳派と三遊派のちがいについて四代目小さんはうまいことをいっている。「総じて柳の方は地味で、三遊は華やか、柳は隠居やお医者が巧く、三遊は若旦那や幇間、つまり天災や猫久が柳なら、湯屋番や干物箱は三遊といったわけ」(「小さん聞書」参照)これでもわかるように柳派はどちらかといえば地味、三遊派は派手で、小さんのこのみに円朝があわないのはあたりまえかもしれない。
ここらへんにくれば、落語通の方々は「そんなもんだろう」と納得されることでしょう。定着化された評価です。
三代目小さんが円朝をくさすのは、こんなところからきているのかもしれませんね。
 成城石井.com ことば 演目 千字寄席 円朝作品
成城石井.com ことば 演目 千字寄席 円朝作品