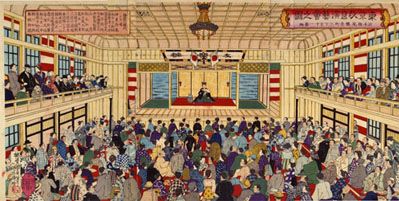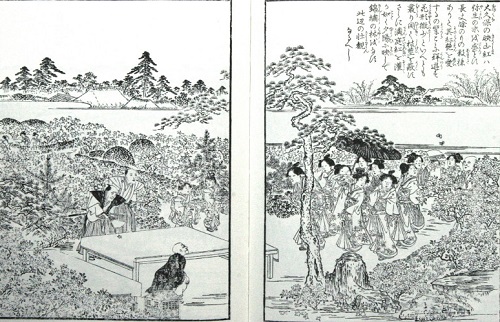成城石井.com ことば 噺家 演目 志ん生 円朝迷宮 千字寄席
成城石井.com ことば 噺家 演目 志ん生 円朝迷宮 千字寄席
【どんな?】
お屋敷で聞きかじった隠し言葉を、長屋でまねる植木屋。
訪れた熊を相手に、植木屋が「おーい、奥や」
女房が「鞍馬山から牛若丸がいでましてその名を九郎判官義経」
女房が先に言ってしまったから、植木屋は「うーん、弁慶にしておけ」
別題:弁慶
【あらすじ】
さるお屋敷で仕事中の植木屋、一休みでだんなから「酒は好きか」と聞かれる。
もとより酒なら浴びるほうの口。
そこでごちそうになったのが、上方の柳影という「銘酒」だが、これは実は「なおし」という安酒の加工品。
なにも知らない植木屋、暑気払いの冷や酒ですっかりいい心持ちになった上、鯉の洗いまで相伴して大喜び。
「時におまえさん、菜をおあがりかい」
「へい、大好物で」
ところが、次の間から奥さまが
「だんなさま、鞍馬山から牛若丸が出まして、名を九郎判官」
と妙な返事。
だんなもだんなで
「義経にしておきな」
これが、実は洒落で、菜は食べてしまってないから「菜は食らう(=九郎)」、「それならよしとけ(=義経)」というわけ。
客に失礼がないための、隠し言葉だという。
植木屋、その風流にすっかり感心して、家に帰ると女房に
「やい、これこれこういうわけだが、てめえなんざ、亭主のつらさえ見りゃ、イワシイワシってやがって……さすがはお屋敷の奥さまだ。同じ女ながら、こんな行儀のいいことはてめえにゃ言えめえ」
「言ってやるから、鯉の洗いを買ってみな」
もめているところへ、悪友の大工の熊五郎。
こいつぁいい実験台とばかり、女房を無理やり次の間……はないから押し入れに押し込み、熊を相手に
「たいそうご精がでるねえ」
から始まって、ご隠居との会話をそっくり鸚鵡返し……しようとするが……。
「青いものを通してくる風が、ひときわ心持ちがいいな」
「青いものって、向こうにゴミためがあるだけじゃねえか」
「あのゴミためを通してくる風が……」
「変なものが好きだな、てめえは」
「大阪の友人から届いた柳影だ。まあおあがり」
「ただの酒じゃねえか」
「さほど冷えてはおらんが」
「燗がしてあるじゃねえか」
「鯉の洗いをおあがり」
「イワシの塩焼きじゃねえか」
「時に植木屋さん、菜をおあがりかな」
「植木屋はてめえだ」
「菜はお好きかな」
「大嫌えだよ」
タダ酒をのんで、イワシまで食って、今さら嫌いはひどい。
ここが肝心だから、頼むから食うと言ってくれと泣きつかれて
「しょうがねえ。食うよ」
「おーい、奥や」
待ってましたとばかり手をたたくと、押し入れから女房が転げ出し、
「だんなさま、鞍馬山から牛若丸が出まして、その名を九郎判官義経」
と、先を言っちまった。
亭主は困って
「うーん、弁慶にしておけ」
底本:五代目柳家小さん
【しりたい】
青菜とは 【RIZAP COOK】
三代目柳家小さん(豊島銀之助、1857-1930)が、上方から東京に移した噺です。
東京(江戸)では主に菜といえば、一年中見られる小松菜をいいます。
冬には菜漬けにしますが、この噺では初夏ですから、おひたしにでもして出すのでしょう。
値は三文と相場が決まっていて、「青菜(は)男に見せるな」という諺がありました。
これは、青菜は煮た場合、量が減るので、びっくりしないように亭主には見せるな、の意味ですが、なにやら、わかったようなわからないような解釈ですね。
柳影は夏の風物詩 【RIZAP COOK】
柳影とは、みりんとしょうちゅうを半分ずつ合わせてまぜたものです。
江戸では「直し」、京では「やなぎかげ」と呼びました。
夏のもので、冷やして飲みます。暑気払いによいとされていました。
みりんが半分入っているので甘味が強く、酒好きには好まれません。夏の風物詩、年中行事のご祝儀ものとしての飲み物です。
これとは別に「直し酒」というのがあります。粗悪な酒や賞味期限を過ぎたような酒をまぜ香りをつけてごまかしたものです。
イワシの塩焼き 【RIZAP COOK】
鰯は江戸市民の食の王様で、天保11年(1840)正月発行の『日用倹約料理仕方角力番付』では、魚類の部の西大関に「目ざしいわし」、前頭四枚目に「いわししほやき(塩焼き)」となっています。
とにかく値の安いものの代名詞でしたが、今ではちょっとした高級魚です。
隠語では、女房ことば(「垂乳根」参照)で「おほそ」、僧侶のことばでは、紫がかっているところから、紫衣からの連想で「大僧正」と呼ばれました。
判官 【RIZAP COOK】
源義経は源義朝の八男ですから、八郎と名乗るべきなのですが、おじさんの源為朝が鎮西八郎為朝と呼ばれることから、遠慮して「九郎」と称していたといわれています。
これは、「そういわれていた」ことが重要で、ならばこそ、後世の人々は「九郎判官義経」と呼ぶわけです。
それともうひとつ。判官は、律令官制で、各官司(役所)に置かれた4階級の幹部職員の中の三番目の職位をいいます。
4階級の幹部職員とは四等官制と呼ばれるものです。
上から、「かみ」「すけ」「じょう」「さかん」と呼ばれました。
これを役所ごとに表記する文字はさまざまです。表記の主な例は以下の通り。
| かみ | 長官 | 伯、卿、大夫、頭、正、尹、督、帥、守 |
| すけ | 次官 | 副、輔、亮、助、弼、佐、弐、介 |
| じょう | 判官 | 祐、丞、允、忠、尉、監、掾 |
| さかん | 主典 | 史、録、属、疏、志、典、目 |
この一覧の字づらを覚えておくとなにかと便利なのですが、それはともかく。
義経は、朝廷から検非違使の尉に任ぜられたことから、「九郎判官義経」と呼ばれるのです。
もっとも、兄の頼朝の許可をもらうことなく受けてしまったため、兄からにらまれ始め、彼らの崩壊のきっかけともなりました。
朝廷のおもわくは二人の仲を裂かせて弱体化させようとするところにありました。
戦うことにしか関心がなくて政治の闇に疎い、武骨で好色な青年はいいカモだったのでしょう。
「判官」は「はんがん」が普通の呼び方ですが、検非違使の尉の職位を得た義経に関しては「ほうがん」と呼びます。
検非違使では「ほうがん」と呼んだらしいのです。
検非違使は「けびいし」と読み、都の警察機関です。
ちなみに、「ほうがんびいき」とは「判官贔屓」のことです。
兄に討たれた義経の薄命を同情することから、弱者への同情や贔屓ぶりを言うわけです。
弁慶、そのココロは 【RIZAP COOK】
オチの「弁慶」は「考えオチ」というやつです。
義経たちの最後の戦いとなった「衣川の合戦」では、主君義経を守るべく、武蔵坊弁慶は大長刀を杖にして、橋の上で立ったまま、壮絶な死を遂げました。
その故事から、「弁慶の立ち往生」ということばが生まれたのでした。
「弁慶の立ち往生」とは、進むことも退くこともできず動けなくなることをいいます。
「うーん、弁慶にしておけ」は、この「立ち往生」の意味を利かせているのです。
亭主が言うべきの「義経」を女房が先に言ってしまったので、亭主は困ってしまって立ち往生、という絵です。
『義経記』に描かれる弁慶立ち往生の故事がわかりづらくなったり、「途方にくれる、困る」という意味の「立ち往生」が死語化している現代では、説明なしには通じなくなっているかもしれませんね。
上方では人におごられることを「弁慶」といいます。これは上方落語「舟弁慶」のオチにもなっています。この噺での「弁慶」には、その意味も加わっているのでしょう。
ところで、弁慶は、『吾妻鏡』の中では「弁慶法師」と1回きりの登場だそうです。まあ、鎌倉幕府の視点からはどうでもよい存在だったのでしょうか。負け組ですから。
それでも、主君を支える忠義な男、剛勇無双のスーパースターとしては、今でも最高の人気を得ています。
小里ん語り、小さんの芸談 【RIZAP COOK】
この噺は柳家の十八番といわれています。
ならば、芸談好きの代表格、五代目柳家小さん(小林盛夫、1915-2002)の芸談を聴いてみましょう。弟子の小里ん師が語ります。
植木屋が帰ったとき、「湯はいいや。飯にしよう」って言うでしょ。あそこは、「一日サボってきた」っていう気持ちの現れなんだそうです。「お客さんに分かる分からないは関係ない。話を演じる時、そういう気持ちを腹に入れておくことを、自分の中で大事にしろ」と言われましたね。だから、「湯はいいや。飯にしよう」みたいな言葉を、「無駄なセリフ」だと思っちゃいけない。無駄だといって刈り込んでったら、落語の科白はみんななくなっちゃう。そこを、「なんでこの科白が要るんだろうって考えなきゃいけない。落語はみんなそうだ」と師匠からは教えられました。
『五代目小さん芸語録』柳家小里ん、石井徹也(聞き手)著、中央公論新社、2012年
なるほどね。芸態の奥は深いです。
「青菜」の演者
三代目小さんが持ってきた話ですから、四代目柳家小さん(大野菊松、1888-1947)も得意にしていました。四代目から五代目に。
柳家の噺家はよくやります。
十代目柳家小三治(郡山剛蔵、1939.12.17-2021.10.7)も引き継いでいました。文句なし。絶品でした。還暦を過ぎた頃からのが聴きごたえありまました。