【植木屋娘】
うえきやむすめ
![]()
 成城石井
成城石井
【どんな噺】
上方噺。松鶴、米朝、枝雀などが演じてきました。
明治期に東京にも移されて、江戸風な物語に変身。
■
【あらすじ】
とあるお寺の門前。
植木屋の看板を出しているのは、元は武士だったという幸右衛門だ。
せっかちだが、腕がよくて、店は順調に繁盛している。
多くの得意先を持つようになって、若い衆も数人雇って、いまは植木屋幸右衛門世間に通っている。
女房のおさじと娘のおみつの3人家族。
娘はべっぴんで、幸右衛門のなによりのご自慢だ。
おみつは今年17歳になる。来年は18、再来年は19歳。
幸右衛門は、婿養子を迎えてぼちぼち隠居したいと考えている。
それというのも、幸右衛門には心に決めた男がいるから。
その男とは、懇意にしている奥のお寺に、住み込みで修行している伝吉。
男前の若い衆だ。
伝吉が奥のお寺に来てからというもの、幸右衛門はその人柄に惚れ込んでいる。
「伝吉さん、伝吉さん」と、なにかと伝吉を頼りにしているのだ。
そんなこんなで、幸右衛門は奥のお寺に日参する。
「かかあ、植木に虫が付いたら、おれは植木屋だからなんとでもできるが、娘に付く虫はおれの手に負えねえ。娘屋じゃねえからな」
幸右衛門、ばかなことを言っては、おさじに自分の思いを話している。
聴いた女房は大きくうなずく。
そばのおみつも、まんざらではないようなそぶり。
それを見た幸右衛門は、善は急げと、奥のお寺に飛び込んだ。
「伝吉さんをおくれ」
藪から棒の申し出に、奥のお寺の和尚はいぶかしむ。
「伝吉は、さる武家の嫡男で修養のために預かっているだけなのじゃ。婿養子に入るなどできない相談じゃな」
素っ気ない返事に、幸右衛門は意気消沈して家に戻った。
こうなれば、作戦変更。
既成事実を作るしかない。
「これだ!」
幸右衛門は一計を案じて、おさじに話した。
その計略とは。
伝吉を家へ招待して酒席を設ける。
最初は4人で歓談する。
すぐに夫婦は用事を言い出して中座する。
おみつと伝吉だけに。
二人きりでのっぴきならないかかわりをつくらせちまおう。
以上、計略完了。
ある日。
伝吉が招きに応じて、幸右衛門の家にやってきた。
「おさじ、湯屋で向かいのばばあと待ち合わせてんだろ。早く行ってこい」
「伝吉さんが来るというので今、行ってきたところですよ」
「ばかやろ、おめえがめかし込んでどうする。もう一度、湯のはしごをしてこいてんだ」
幸右衛門、女房のおさじを外に出させる。
伝吉と一献やりとりしたところで、今度は幸右衛門。
「あ、いけねえ。得意先へ植木を持って行くのを忘れちまった。おれも中座するが、娘と続けておいてくだせえ。すぐに戻ってきやすから、待っといておくれよ。……だけど、そんなにすぐではありませんぜ。なにかをする時間はたっぷりあるてもんで。うふふ。娘をよろしく、で」
そう言って、幸右衛門は外へ出た。
幸右衛門は裏へ回って、焼き板塀に顔をくっつけて節穴から部屋をのぞく。
顔を黒くして自分の家をのぞいている幸右衛門を見て、近所の連中がけげんに思う。
そこを幸右衛門、「えへへ」と笑ってごまかし、さらなる二人のようすをうかがうことに。
おみつと伝吉、二人は仲睦まじく話をしている。ただそれだけ。
おみつが酒を断るので、伝吉も酒を控えて、二人の気分は盛り上がらないでいる。
伝吉がおみつの手でも握ったら、とたんに飛び込んでいって、めおとの約束をさせようかと。
そんな幸右衛門の思いも、はずれる。
「娘に酒を教えておけばよかったなあ」
幸右衛門は、いまさら後悔しても手遅れだ。
やがて伝吉がおみつに言い出す。
「親方、門遅いですね。ぼちぼちおひらきにしましょうか」
そう言って、伝吉は腰を上げるしまつ。
おみつおみつで、ぼーっとして、なにもせずにただ見送るだけ。
「ばかやろ、引き止めろてんだ」
幸右衛門が胸の内で叫んでも、もう手遅れ。
作戦はみごと、失敗に終わった。
そこへ、湯あたりしたおさじが、ふらふらになって戻ってきた。
「どこへ行ってたんだよ。おい。この大事な時に。おめえのしつけがよすぎて、ぶちこわしだぜ」
幸右衛門は、おさじにうっぷんをぶつけるだけで、もう、あとのまつり。
数日後。
向かいのばばあが駆け込んでくる。
「おみつちゃんが身ごもってるよ」
おさじはびっくり。
「なんで」
「なんでって、湯屋でたしかめたんだよ」
その顛末を聞いて、激怒する幸右衛門。
おさじは幸右衛門をなだめて二階へ上がらせる。
はしご段の下で、幸右衛門に聞こえるように、おさじがおみつをただす。
娘ははらぼて(妊娠)を認めた。
「相手は奥のお寺の伝吉さんです」
母親が驚く。
「なんだって。相手は奥のお寺の伝吉さんだって?」
おさじが大声で叫ぶと、幸右衛門が二階から転げ落ちてきた。
「おお、おみつ、よくやった。よく取った。今から奥のお寺へ行って話をまとめてくるぜ」
幸右衛門は外へ飛び出し、奥のお寺に向かっていった。
「和尚さん、伝吉さんを養子にもらいたい」
「あれは五百石の家督を継がなくてはならんのじゃ」
「うちのおみつは、はらぼてになっちまって」
「なに、伝吉があんたの娘のはらを……か」
「大きくしてくれたんだ。うちの根分けから接ぎ木から、みんな仕込んで、な」
「それはありがたいことじゃが、あれは五百石の家督を相続しないと」
「それもなるようにする。五百石でも八百石でも継がせるんで」
「いくらなんでも、お侍の家を取ったり継いだりは」
「取ったり継いだりは、うちの秘伝なんで」
【しりたい】
オチが不思議
オチがなんだかわかりにくいです。
要は、幸右衛門が段取りする日の前から、伝吉とおみつはできていた、ということなのですね。
「案ずるより産むがやすし」とは、まさにこのことでしょうか。
噺の背景
もとは上方噺です。
ところが、明治期に東京に移ってきて、いかにも江戸風の噺にさまがわりしました。
それというのも、江戸の八割は武家地(六割)と寺社地(二割)がしていて、この大半は庭があったわけですから、植木の需要はかなりのもとなっていました。
足軽や同心のような下級武士でも宅地には庭を持っていたわけで、彼らが庭を利用した植木(園芸)を内職(副業)に精出していたからです。
江戸の町では、江戸時代の前期には椿、桜、つつじなど花木中心でしたが、後期には菊、朝顔、桜草、菖蒲など花卉(くさばな)中心に流行が変わっていきました。
前期では、染井で多種の花木が栽培されて、駒込、千駄木、根津といった本郷台地の東斜面に広がりました。
後期では、本郷台地西斜面での菊、堀切での菖蒲、巣鴨、庚申塚、板橋(中山道沿い)の農家が桜草を栽培して、街場に売りに行っていたのでした。
このような流れに追随するかように、江戸住まいの下級武士の間で、植木が副業として発展していきました。
武士は下級であっても庭を広く持っているものです。そこに植栽して売る、という応用をしたのですね。
好例は、大久保のつつじです。
いまの新宿区百人町ですが、江戸時代には、大久保百人組と呼ばれた、伊賀組鉄砲百人同心の組屋敷がありました。
彼らは経済的に困窮していました。
しかも彼らは組織的集団的行動に長けていました。
一糸乱れることなくつつじを栽培しては、観覧させたり売ったりして、小金を稼いだのです。
つつじは染井や巣鴨も有名でしたが、大久保に比べれば、その千分の一といわれるほど、大久保のつつじは第一だったようです。
江戸のこのような光景は、幕末維新期に来日したロバート・フォーチュン(1812-80、英庭師)やラザフォード・オールコック(1809-97、英医師、外交官)などには大いに注目するところとなりました。
フォーチュンもオールコックも、名うてのプラントハンターです。
やがて、ロンドンのキュー植物園や英ヴィーチ商会を中心とした、ヨーロッパの花卉ブームに大きな影響を与えていったのでした。
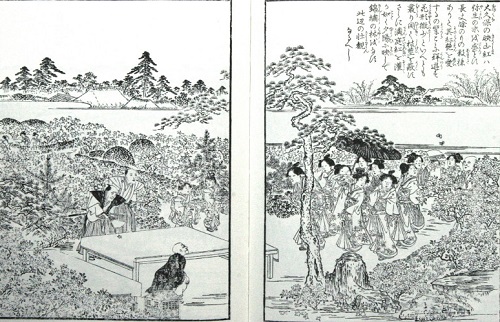
植木屋
植木屋というのは、庭園の管理、造庭、植物の育成、販売を、一括で行う職人をさします。
植物の形状を整え、もっとも美しい状態で花を咲かせる栽培技法、奇種植物の採集、新品種の創出など、時代ごとの状況や流行に応じて、園芸にかかわる技術と美意識をたかめていくのが、当時の植木屋の役回りでした。
このように、たんなる職人とも言い難く、花木・花卉にかかわるすべてについてのめんどうをみるのが、植木屋という職業の本質でした。
言い方を変えれば、対象となる事物を総合的、総括的にかかわるのが当時の職人だったということなのでしょう。
この噺は、東京に移り上方噺を活躍した二代目桂小南(谷田金次郎、1920-96)がやっていました。師匠筋の二代目桂小文治(稲田裕次郎、1893-1967)の型を引き継いでいました。
![]()





