【町内の若い衆】
ちょうないのわかいしゅう
【どんな?】
すごいオチですね。
さすが。
長屋のかみさんは太っ腹!
別題:鉢山嬶(上方) 類話:氏子中
【あらすじ】
長屋の熊五郎、兄貴分の家に増築祝いに寄ると、かみさんが、今組合の寄り合いに出かけて留守だと言う。
熊がお世辞ついでに、兄貴はえらい、働き者でこんな豪勢な建て増しもできて、組合だって兄貴の働き一つでもっているようなもんだと並べると、このかみさんの言うことが振るっている。
「あら、いやですよ。うちの人の働き一つで、こんなことができるもんですか。言ってみれば、町内の皆さんが寄ってたかってこさえてくれたようなもんですよ」
熊公、この言葉のおくゆかしさにすっかり感心してしまい「さすがに兄貴のとこのかみさんだ。それに引き換え、うちのカカアは同じ女でありながら」と、つくづく情けなくなった。
帰るといきなり「どこをのたくってやがった」とヘビ扱い。
てめえぐれえ口の悪い女はねえ、これこれこういうわけだが、てめえなんざこれだけの受け答えはできめえと説教すると「ふん、それくらい言えなくてさ。言ってやるから建て増ししてごらん」
痛いところを突かれる。
形勢が悪いので「湯ィへえってくる」と言えば「ついでに沈んじゃえ。ブクブク野郎」
熊公が腹を立て「しらみじゃねえが、煮え湯ぶっかけてやろうかしらん」と考えながら歩いていると、向こうから八五郎。
そこで熊「カカアの奴、ああ大きなことを抜かしゃあがったからには、言えるか言えねえか試してやろう」と思いつき、八五郎に「オレが留守のうちに何かオレのことをほめて、うちの奴がどんな受け答えをするか、聞いてきてくんねえ」と頼む。
一杯おごる約束で引き受けた八五郎、いきなり熊のかみさんに「あーら、八っつあん、うちのカボチャ野郎、生意気に湯へ行くなんて出てったけど、どうせあんなツラ、洗ったってしょうがないのにさ。あきれるじゃないか」
先制パンチを食らわされ、目を白黒させたが、なにかほめなくてはとキョロキョロ見回しても、何もない。
畳はすりきれている。土瓶は口がない。かみさんは臨月で腹がせり出している。
これだと思って「いやあ、さすがに熊兄ィ。この物価高に赤ん坊をこさえるなんて、さすが働き者だ」
するとかみさんが「あら、いやですよ。うちの人の働き一つでこんなことができるものですか。言ってみれば、町内の皆さんが寄ってたかってこさえてくれたようなもんですよ」
出典:五代目古今亭志ん生
【しりたい】
原話もそのまま 成城石井.com
たいていの噺は、原典があっても長い年月を経ているうちにかなりストーリーが変わってくるものですが、この「町内の若い衆」ばかりは最古の原話とされる元禄3年(1690)刊の笑話本『枝珊瑚珠』中の「人の情」以来、大筋はまったく同じなんです。
この笑話集は、江戸落語の始祖といわれる鹿野武左衛門(1649-99)の手になるものですが、それから1世紀を経た寛政10年(1798)刊の『軽口新玉箒』中の「築山」になると、オチの女房のセリフが「これも主(=主人)ばかりでなく、内の若い衆の転合(てんごう。いたずら)にこしらえました」と、よけいエスカレートしています。
いかに「若い衆がよってたかって」のオチにインパクトが強かったかがわかろうというものです。
「こさえてくれた」でご難 成城石井.com
このたった一言のおかげで、あわれ、この噺はアジア太平洋戦争の間は禁演落語の一つに指定され、長瀧山本法寺(日蓮宗、台東区寿町2-9-7)の「はなし塚」に葬られていました。
五代目古今亭志ん生(美濃部孝蔵、1890-1973)がまだ七代目金原亭馬生だったころの昭和10年(1935)2月、レコードに吹き込んだ「町内の若い衆」の速記が残っています。
問題の最後の部分は「こさえてくれた」ではとても検閲を通らず、「育ててくれた」という、おもしろくもおかしくもないものになっています。
昭和10年の時点までは、こんな程度のゴマカシで、エロ落語もかろうじて命脈を保っていたことになります。
はなし塚が建立されて53席の噺が葬られたのは、昭和16年(1941)10月31日のことでした。
もっと強烈な「氏子中」 成城石井.com
前述の志ん生の速記は、実はタイトルが「氏子中」で、長男の十代目金原亭馬生(美濃部清、1928-82)も同じ題で「町内の若い衆」を演じています。
ところが、同じ不倫噺でも本来、この二つは別話なんですね。
「氏子中」の項目を見ていただければおわかりになると思いますが、ここでは、そっちを見るのもめんどうな方のために、さわりを記しておきます。
商用の旅から一年ぶりに帰った亭主の与太郎が、女房が妊娠しているのを見て、驚いて問いただすと、女房もさるもの、氏神の神田明神に願掛けして授かった子だと、しらばっくれる。親分に相談すると、「子供が産まれたら、祝いに友達連中を呼んで荒神さまのお神酒で胞衣(えな。胎盤)を洗えば、胞衣に本当の父親の紋が浮かび出る。そいつに母子ともノシつけてくれてやれ」そこで、言われたとおりにすると、「神田大明神」の文字がくっきり。疑いが晴れたかに見えたが、よくよく見ると横に「氏子中」。
こちらは、五代目三遊亭円楽(吉河寛海、1932-2009)がたまに演じていました。
『艶本 葉男婦舞喜』から 成城石井.com
この噺を絵にすると、こんなかんじでしょうか。
下の絵は、喜多川歌麿(北川信美、1753-1806)の『艶本 葉男婦舞喜』に収録されています。
「えほん はなふぶき」という、歌麿の有名な春画本の中の一枚ですね。
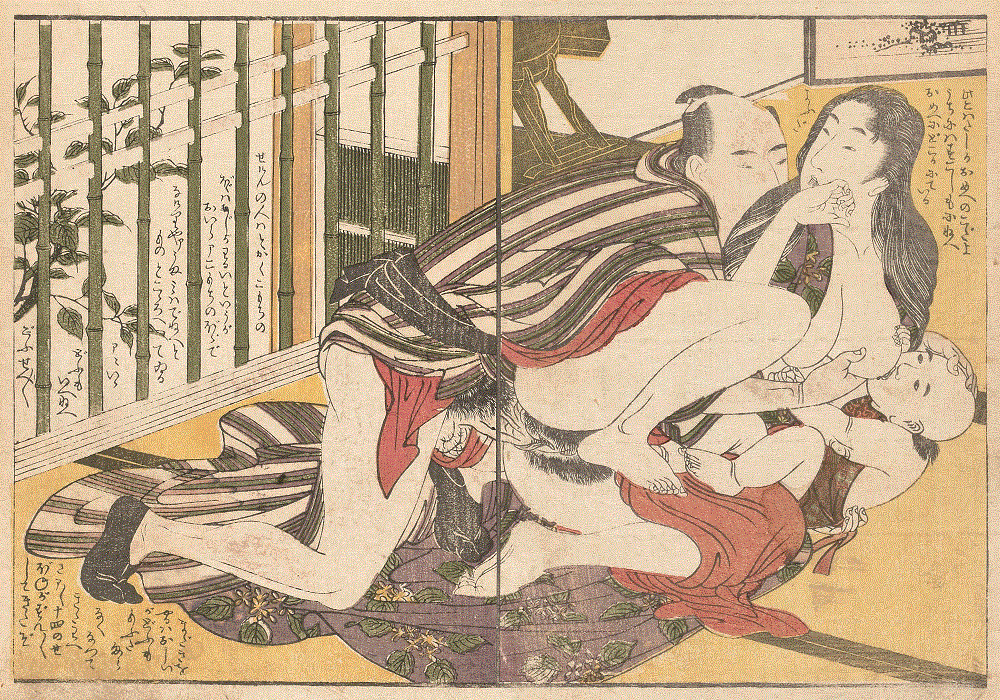
喜多川歌麿『艶本 葉男婦舞喜』上巻第七図より
この絵の書き入れ(絵のまわりにちりばめられた文字)は男女の会話です。じつは、こんなことを話しているのです。現代語訳にしてみました。
女「この子は確かおめえの子だよ。うちの亭主には少しも似ねえ。おめえにどこか似ているようだ」
男「世間の人は、とかく子持ちのぼぼは味が悪いというが、おいらあ、子持ちのぼぼでなけりゃアうま味は出ねえものと心得ている。あああ、いい。どうも言えねえ。豪勢、豪勢。まだ気をやるのは惜しいが、どうももう、たまらなくなってきた。さあさあ、十四の背骨がずんずんしてきたぞ」
絵に出ている子供はどうやら、おかみさんと「町内の若い衆」との子のようです。女は「あんたの子だよ」なんて詰め寄っているのに、男は「子持ちのぼぼがいい」とかほざいて、どこ吹く風。この子の認知をしません。会話のちぐはぐがなんとも笑いを誘います。
ひとつ、蛇足を。この絵では子供が乳を吸っています。乳を吸われると締まりがよくなるため、それを好んで男が挑むのだそうです。ということは、この男女はなかなかな手練れなのかもしれませんね。
参考文献:車浮代『歌麿春画で江戸かなを学ぶ』(中央公論新社、2021年)





