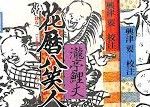【野ざらし】
のざらし
幽霊と濡れる?
【どんな?】
釣りの帰途、川べりに髑髏。
手向けの酒で回向を。
宵になれば。
お礼参りの幽霊としっぽりと。
秋を感じさせる噺です。
別題:手向けの酒 骨釣り(上方)
【あらすじ】
頃は明治の初め。
長屋が根継(改修工事)をする。
三十八軒あったうち、三十六軒までは引っ越してしまった。
残ったのは職人の八五郎と、もと侍で釣り道楽の尾形清十郎の二人だけ。
昨夜、隣で
「一人では物騒だったろう」
などと、清十郎の声がしたので、てっきり女ができたと合点した八五郎、
「おまえさん、釣りじゃなくていい女のところへ行くんでしょう?」
とカマをかけると
「いや、面目ない。こういうわけだ」
と清十郎が始めた打ち明け話がものすごい。
昨日、向島で釣りをしたら「間日(暇な日)というのか、雑魚一匹かからん」と、その帰り道、浅草寺の六時の鐘がボーンと鳴ると、にわかに葦が風にざわざわ。
鳥が急に茂みから飛び立ったので驚き、葦の中を見ると野ざらしになった髑髏が一つ。
清十郎、哀れに思って手向けの回向をしてやった。
「狸を食った? ひどいね」
「回向したんだ」
「猫もねらった」
「わからない男だ。五七五の句を詠んでやったのだ。一休和尚の歌に『骨隠す皮には誰も迷うらん皮破れればかくの姿よ』とあるから、それをまねて『野を肥やせ骨の形見のすすきかな』と浮かんだ」
骸骨の上に持参した酒をかけてやり、いい功徳をしたと気持ちよくその晩寝入っていると、戸をたたく者がいる。
出てみると女で
「向島の葦の中から来ました」
ぞっとして、狸が化かしに来たのだろうとよく見ると、十六、七の美しい娘。
娘の言うには
「あんなところに死骸をさらし、迷っていましたところ、今日、はからずもあなたのご回向で浮かぶことができましたので、お礼に参りました。腰などお揉みしましょう」
結局、一晩、幽霊としっぽり。
八五郎、すっかりうらやましくなり、自分も女を探しに行こうと強引に釣り竿を借り、向島までやってきた。
大勢釣り人が出ているところで
「ポンと突き出す鐘の音は陰にこもってものすごく、鳥が飛び出しゃコツがある」
と能天気に鼻歌を唄うので、みんなあきれて逃げてしまう。
葦を探すと骨が見つかったので、しめたとばかり酒をどんどんぶっかける。
「オレの家は門跡さまの前、豆腐屋の裏の突き当たりだからね。酒肴をそろえて待っているよ、ねえさん」
と、俳句も何も省略して帰ってしまった。
※現行はここで終わり。
これを聞いていたのが、悪幇間の新朝という男。
てっきり、八五郎が葦の中に女を連れ込んで色事をしていたと勘違い。
住所は聞いたから、今夜出かけて濡れ場を押さえ、いくらか金にしてやろうとたくらむ。
一方、八五郎、七輪の火をあおぎながら、今か今かと待っているがいっこうに幽霊が現れない。
もし門違いで隣に行ったら大変だと気を揉むところへ、
「ヤー」
と野太い声。
幇間、
「どうもこんちはまことに。しかし、けっこうなお住まいで、実に骨董家の好く家でゲスな」
とヨイショを始めたから、八五郎は仰天。
「恐ろしく鼻の大きなコツだが、てめえはいったいどこの者だ」
「新朝という幇間でゲス」
「太鼓? はあ、それじゃ、葦の中のは馬の骨だったか」
【しりたい】
元祖は中華風「釜掘り」
原典は中国明代の笑話本『笑府』中の「学様」で、これは最初の骨が楊貴妃、二番目に三国志の豪傑・張飛が登場、「拙者の尻をご用立ていたそう」となります。
男色めいたオチです。
さらに、これの直接の影響か、落語にも古くは類話「支那の野ざらし」がありました。
こちらは『史記』『十八史略』の「鴻門の会」で名高い樊會が現れ、「肛門(=鴻門)を破りに来たか」という、これまた男色めいたオチです。
この噺は、はじめから男色(釜掘り)がつきまとっていました。
上方では五右衛門が登場
上方落語では「骨釣り」と題します。
若だんなが木津川へ遊びに行き、そこで骨を見つける演出で、最後には幇間ではなく、大盗賊・石川五右衛門登場。「閨中のおとぎなどつかまつらん」「あんた、だれ?」「石川五右衛門」「ああ、やっぱり釜に縁がある」。
言うまでもなく、釜ゆでとそっちの方の「カマ」を掛けたものです。こちらも男色がらみ。どうも今回は、こんなのばかりで……。
それではここらで、正統的な東京の「野ざらし」を、ちょっとまじめに。
因果噺から滑稽噺へ
こんな、尻がうずくような下品な噺では困ると嘆いたか、禅僧出身の二代目林屋正藏(不詳-不詳、沢善正蔵、実は三代目)が、妙な連中の出現するオチの部分を跡形もなくカット、新たに仏教説話的な因果噺にこしらえ直しました。これは陰気な噺。
二代目正蔵は「こんにゃく問答」の作者ともいわれます。仏教がらみの噺の好みました。でも、陰気になる。
明治期に、それをまたひっくり返したのが、初代三遊亭円遊(竹内金太郎、1850-1907、鼻の、実は三代目)。明治の爆笑王です。
初代円遊は「手向けの酒」の題で演じています。
男色の部分を消したまま、あらすじのような滑稽噺としてリサイクルさせました。円遊の「手向けの酒」が『百花園』に載ったのは明治26年(1893)のこと。
さらに、二代目三遊亭円遊(吉田由之助、1867-1924、実は四代目)が改良。八五郎の釣りの場面を工夫して、明るくにぎやかにしました。それ以降は、二代目円遊の形が通行します。
「野ざらしの」柳好、柳枝
昭和初期から現在にいたるまでは、初代円遊→二代目円遊の型が広まります。
明るくリズミカルな芸風で売った三代目春風亭柳好(松本亀太郎、1887-1956、野ざらしの、向島の、実は五代目)、端正な語り口の八代目春風亭柳枝(島田勝巳、1905-59)が、それぞれこの噺を得意としました。
特に柳好は「鐘がボンと鳴りゃ上げ潮南……」の鼻唄の美声が評判で、「野ざらしの……」と一つ名でうたわれました。
柳枝も軽妙な演出で十八番としましたが、サゲ(オチ)までやらず、八五郎が骨に酒をかける部分で切っていました。現在はほとんどこのやり方が横行しています。
現在も、よく高座にかけられています。
TBS落語研究会でも、オチのわかりにくさや制限時間という事情はあるにせよ、こういう席でさえも、途中でチョン切る上げ底版がまかり通っているのは考えものです。
馬の骨?
幇間と太鼓を掛け、太鼓は馬の皮を張ることから、しゃれただけです。
牡馬が勃起した陰茎で下腹をたたくのを「馬が太鼓を打つ」というので、そこからきたという説もあります。
門跡さま
「門跡」の本来の意味は、祖師(宗派の教祖)の法灯(教え)を受け継いでいる寺院のこと。
京都には「門跡さま」は多数ありますが、江戸で「門跡さま」といえば、浄浄土真宗東本願寺派本山東本願寺のこと。これでは長すぎて言えません。一般には「浅草本願寺」と呼ばれていました。
四代目橘家円喬(柴田清五郎、1865-1912)が、誘われてこの寺院で節談説教(僧が言葉に抑揚を付け、美声とジェスチャーで演技するように語りかける説教)を聴いた際、説教僧が前座、二ツ目、真打ちの階級制度、高座と聴者の仕掛けなどが寄席とそっくりなことにびっくりした、という逸話が残っています。
浅草本願寺は、京都の東本願寺とは本院と別院の関係でしたが、昭和40年(1965)に関係を解消して、独立しています。通称も、浅草本願寺から東京本願寺へと変更されました。
「野ざらし」の江戸・明治期には、東本願寺の名称で、浄土真宗大谷派の別院でした。「門跡さま」で通っていたわけです。
時の鐘
江戸では、人々に時を知らせる鐘、幕府公認の鐘は全部で九か所にありました。以下の通りです。
石町の鐘
中央区日本橋室町4丁目。現在、十思公園(中央区日本橋小伝馬町1丁目)に保存されてあります。
入江町の鐘
墨田区本所入江町2丁目の南。現在の墨田区緑4丁目の大横川沿いにありました。この近所には入江町の岡場所がありました。
上野の鐘
上野の文殊堂前稲荷坂にありました。寛文9年(1669)の創建。稲荷坂は穴稲荷(現在の花園神社)にのぼる坂です。この鐘は、台東区上野公園内、上野精養軒前に保存されてあります。この鐘の音色が江戸でいちばんと好評でした。あんまりよい音なので、二度聴こえたそうで、「上野の二つ鐘」と呼ばれるほどでした。左甚五郎が鐘に龍を彫ったところから、夜な夜な不忍池に水を飲みに出かけるといわれたものがありました。ながらく、上野の鐘とされてきたのですが、これはまちがいで、左甚五郎作の鐘は、上野の鐘は鐘でも時の鐘ではなく、寛永寺の儀式に使われた鐘のことでした。こちらは彰義隊の戦争で焼失したとのことです。
浅草の鐘
弁天山の鐘。寛永13年(1636)に焼失しましたが、三代家光が200両を下賜して再建させました。これも元禄の大火で焼失したそうです。ここからがあやしい。台東区浅草2丁目、浅草寺境内の弁天山に保存されたそうです。元禄の大火というのは三度ありましたが、浅草に及んだ火事は、元禄16年(1703)の火事のもの。小石川の水戸藩上屋敷から出火、本郷から浅草を経て隅田川を越えて本所や深川にまで類焼しました。湯島天神(湯島天満宮)や湯島聖堂なども焼失しました。現存する鐘は、元禄5年(1692)に再建されたものとされているのですから。再検証の必要が残ります。
芝切り通しの鐘
港区芝公園3丁目の内。芝の鐘は当初、西久保八幡の境内にありました。鐘が割れたために、延宝2年(1674)に再建され、愛宕下の青松寺(萬年山、曹洞宗、港区愛宕2丁目)の西隣、芝の切り通しと呼ばれる場所に置かれました。「芝浜」に登場する時の鐘はこちらのものです。
市谷八幡の鐘
新宿区市谷八幡。市谷八幡の境内に設置されていました。市谷八幡とは、亀岡八幡宮のことです。これは鎌倉の鶴岡八幡を分祀勧請したものです。神仏習合で、明治初期までは東圓寺という別当寺もありましたが、廃寺に。現在は、時の鐘もありません。
赤坂成満寺の鐘
当初は一ツ木の円通寺(仏智山、日蓮宗、港区赤坂5丁目)にありましたが、その後、成満寺(浄土真宗大谷派)に移されました。成満寺は昭和36年(1961)に多摩市に移転しています。成満寺があった場所は、現在の田町通りとみすじ通りにはさまれた月世界ビル(赤坂3丁目)あたりだそうです。時の鐘は昭和50年(1975)に円通寺に戻されたそうです。
目白の鐘
新長谷寺(東豊山、真義真言宗豊山派)は目白不動ですが、ここの前に設置されていたそうです。新長谷寺は昭和20年(1945)廃寺となり、目白不動尊は金乗院(神霊山、真義真言宗豊山派、豊島区高田2丁目)に移されました。
四谷天龍寺の鐘
天龍寺(護本山、曹洞宗、新宿区新宿4丁目)に置かれました。寛永寺が表鬼門を守る寺とされるのに対し、天龍寺は裏鬼門を守る寺ということで、護本山という山号なのだそうです。境内に鐘が保存されています。ここの鐘だけは、他よりも半時早く撞いたそうで、新宿の遊里を控えていることから「追い出しの鐘」と呼ばれて評判は悪かったとか。
※『四谷區史』によれば、以下の通り。
相州小田原大慈院末であつて、四谷追分にある曹洞宗、護本山天龍寺は寺格も獨禮であるから昔時は四谷第一の巨刹であり、境内拝領地壹萬二千二百九坪貮合七勺を有した。開闢起立に關しては、文政書上げに、「護本山天龍寺者遠州倉見領西郷村瀧谷法泉寺七代目心翁と申僧住持之節、天文廿三年十一月八日西月友船公ヲ焼香仕、就夫法泉寺ヲ御當地江以上意引来候。其由来は右西月友船公台徳院様御母公寶臺院様之御親父に御座候、依之権現様關東御入國之砌、本多佐渡守様江被仰付、友船公位牌御當地江引移候様被仰付、則心翁儀右位牌持参仕、法泉寺引来、於牛込寺地被下置、寺號を天龍寺と開闢被仰付、則友船公被爲成開基、爲花供具料境内三萬六千坪被下置、心翁住持仕候、其後程過、寛永十一戌年同十二亥兩年貮萬坪餘爲御用地被召上、境内も狭く、友船公之御供具等も不如意に候得共、右御由緒故明暦三年大火事之節從手前奉願、八王子千人衆之宿を仕、御城御普請も成就仕、其後御城被爲召、松平伊豆守殿安藤右京進殿?安藤治右衛門殿松田六郎左衛門殿御立合、伊豆守殿被仰渡候は、此度千人同心之宿仕段上聞、御喜悦被思召候、依之白銀五百枚被下置、御城下寺院雖多、大切之折柄御用達候上は、何様之儀有之候共、寺地異變有之間鋪由被仰渡候、同翌年台徳院様貮拾七年之御忌御相當之節、拙寺八代乾界と申僧、段々御起立之御由緒申上、爲御法事千人江湖執行仕候、其後焼失仕候得共、最前被仰渡候儀申上候得ば、寺地其通罷在候、然處天和三癸亥年類焼仕候處、爲御用地被召上、四谷新宿之先追分におゐて、只今の寺地壹萬貮千貮百九坪貮合七勺之場所拝領仕候、右前段御起立之御由緒を以、前々御年禮之節も乗輿獨禮相勤、壹束壹本兩御本丸江献上仕、?御代替之節も於大廣間獨禮座一同御禮申上、壹束壹本献上仕候、於檜間時服拝領、且納經拝禮相勤、御施物三拾貫文頂戴仕候。是則最初御取立之御趣意を以、寺格に對し被成下候儀と難有奉存候」と見えて、幕府は特別の待遇を與へたのであつた。牛込時代の三萬餘坪は今の納戸町細工町に亘る地であり、その天龍寺と號したのは、遠州瀧谷は天龍川上であつたからである。
開山春屋宗能和尚は康正二年三月十九日を以て寂した。小田原大慈院大綱和尚の弟子であつた。開基に關しては遠く遠州瀧谷時代のことであり、その後度々類焼の厄に遇うて舊記もなく不明である。江戸に於る中興開山は心翁永傳和尚で寛永十四年十一月二十八日に寂した。遠州佐野郡西郷村法泉寺禅鑑和尚の弟子であつた。中興の開基を西月友船禅定門とすること前記の如くであるが、この人は俗名を戸塚五郎太夫忠春と稱し、天文二十三年十一月八日陣歿した遠州法泉寺の代々の壇方であつた。これに寶臺院殿も開基に加へてゐる。從て本堂には本尊千手観音の外に開基二人の位牌を安置したが、何れも家康自鉈を以て作つたものである。
富岡八幡の鐘
この九か所は幕府公認の時の鐘でしたが、川向こう(隅田川の東側)には入江町の鐘しかありませんでしたので、どうしてももうひとつふたつ欲しいところでした。
そこで、俗に「八幡鐘」「山鐘」と呼ばれた、富岡八幡宮(江東区富岡1丁目)の鐘を、時鐘としました。公認ではありません。近辺の茶屋が費用や経費を出し合っての鐘でした。
松平定信による寛政の改革(天明7年=1787-寛政5年=1793)の野暮政治で、吉原がぐっと廃れました。公許の遊里が衰退した代わりに、深川の遊里が栄え始めました。そこで生成されたのが、粋という美的概念でした。
そんなわけですから、ここらへんに時の鐘が必要となってきたのです。
撞いてくりゃるな 八幡鐘よ かわいいお人の 目をさます
撞いておくれな 八幡鐘よ 早くお客を 帰したい
こんな端唄や都々逸が残っています。
落語で「八幡鐘」と出てくれば、富岡八幡の時の鐘、というのが通り相場です。市谷八幡の鐘ではありません。
捨て鐘は三つ
ちなみに、鐘は最初、三つ鳴ります。これは「捨て鐘」というものです。試しに鳴らすおしるし。ですから、実際に撞いた数から三つを引いた数が時報となります。
六つ(午前六時頃の朝六つ、午後六時頃の暮れ六つ)なら、捨て鐘の三つ+時報の六つ=九つ撞いた、ということになります。
いちばん数の多い時報は九つ(午前零時頃の夜九つ、正午頃の昼九つ)、捨て鐘の三つ+時報の九つ=十二撞いた、というもの。
逆に、いちばん少ない数の時報は四つ(午前十時頃の朝四つ、午後十時頃の夜四つ)で、捨て鐘三つ+時報の四つ=七つ撞いた、ということになります。
どちらにしても、一つや二つの鐘はない、ということです。時報の鐘の音は長かったのですね。
 |
|
新品価格 |