【合従連衡】
がっしょうれんこう
従=縦、衡=横
外交上の駆け引き。連合したり同盟したりすること。
従は縦。衡は横。
中国、戦国時代のことです。
一強を誇る西方にあった秦と、燕、斉、趙、魏、韓、楚の東方にあった六弱とが、息の長い攻防戦をめぐっていました。
蘇秦と張儀は、鬼谷子(鬼谷先生)に学んだ縦横家です。
鬼谷子は実在したかどうかも不明ですが、斉の人で、遊説術を教えた人だったようです。
斉の宣王(?-前301)は学問が好きで、斉の首都である臨淄(山東省淄博市)に学者を呼んで議論をさせました。
この学者たちを稷下の学士といいます。その議論の状態を、百家争鳴といいました。
諸子百家の人々です。
そのなかに、鬼谷子もいたかどうか。それもよくわかりません。
『史記』によれば、蘇秦と張儀の師匠だったとあります。
いまでいう、国際謀略の術を授けたのだそうです。
その術をあやつる人を、縦横家と呼びました。
縦横家とは、はかりごとを各国に説いて回る人。これも諸子百家の一です。
まずは蘇秦。合従の策を編み出しました。
合従は、西の秦に対して東の六国が縦(南北)に連合して対抗する策です。
これに対して、連衡は、六国がそれぞれ秦と同盟を結ぶという策。秦と相手国の関係を横(東西)と見たわけです。
こちらは張儀が提唱しました。
この結果、六国の連合が分断され、秦が次々と倒して覇者となりました。
蘇秦や張儀のようなといいました。はかりごとをめぐらす人を縦横家と呼ぶこともあります。
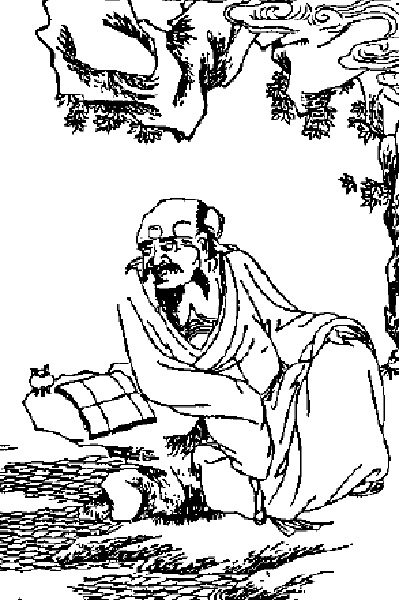
鬼谷先生。仙人みたいです☛






