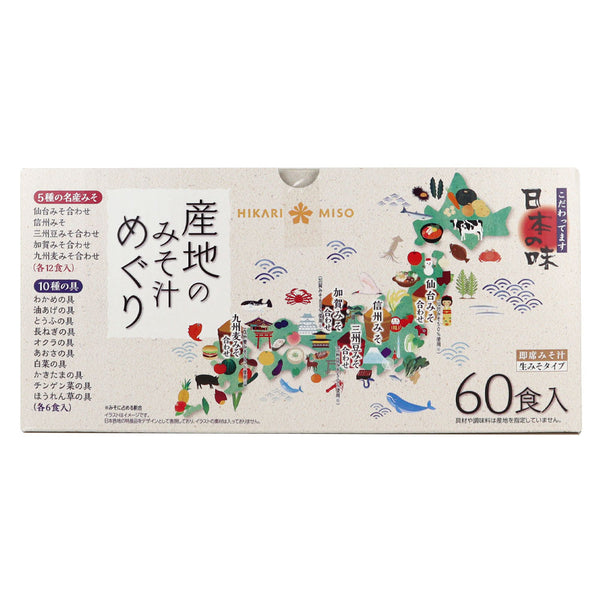【匙加減】
さじかげん
味なお裁き
【どんな噺】
大岡政談のひとつ。
なんとも痛快なお裁きものです。
【あらすじ】
享保の頃。
三田に阿部玄渓という名医がいた。
その息子の玄益は二十五歳で、医道の腕はいいが、まじめ一辺倒の堅物男。
気晴らしは神社仏閣めぐりという、なんとも色気がない。
今日も今日とて、川崎大師にお参りに向かった。
帰りは雨模様となって、途中の品川宿で、急きょ、雨宿りとなる。
なんでもいいからと、狩野屋なる茶店に上がった。
美しい芸妓が現れた。うぶがちな色気が漂う。お奈美という。
神のおぼしめしか。
玄益はお奈美にひとめぼれ。
翌日からは、狩野屋通いに精出す始末。
玄益はやることなすこと、すべてが一本気の構えだ。
やがて手持ちも不如意となり、ついには、父親の医書を質入れして、金の算段に。
それがばれて、父からは勘当とあいなった。
なんとも絵にかいたような放蕩の顛末。
この一件で、はたと目が覚めた玄益。
心を入れ替えて、実家を離れる。
八丁堀の一隅に「医」の看板を掲げる。
今度は、医道に一本気に突き進んだ。
一心不乱、精進し続けて、玄益ならぬ現役丸出しの評判医へと。
一本気と一心不乱で、二年がたった。
ゆとりを見せた玄益。
「少し休んだくらいでも、減益とはなるまい」
南の品川宿へ。
狩野屋にあがり、なじみだったお奈美に会おうとした。気にはなっていたのだ。
えびす顔で出てきたのは、狩野屋主人。
かつては贔屓として、顔なじみだった男。だが、こんな顔には用はない。
「若先生、二年前に、お奈美と夫婦の約束をしたんですかい」
そう聞かれて玄益、あたまをかきかき、苦い白状となる。
「ははは、冗談にも、そんなことを言ったやもしれませんなあ」
「それそれ。お奈美は、若先生のそれを本気にしていましたんで。さりながら、若先生はまもなく勘当のおん身に。ここへも来られなくなっちまいましてね。お奈美は『そのうちに若先生が迎えに来る』と信じているうちに、二年たちまして。とうとう、気がおかしくなっちまいました。ぶらぶら病で。そもそも、お奈美は松本屋義平の抱え芸者でして。ぶらぶら病では、座敷へ出すこともできませんので。今じゃあ、店奥の座敷牢に入ってるんですよ」
主人の話を聞き、驚いた玄益。
「ややっ。いやはや、面目ない。それでは、わたしがお奈美を引き取りましょうぞ」
とは、大胆な告白。
内心ほくそえんだのは狩野屋。
「そんなら、あたしが松本屋へ話をつけますんで、三両出してくださいな」
玄益からの三両を手にした狩野屋は、その後さっそく、松本屋へ出向いた。
「お奈美を若先生に追っ付けましょうよ。三両出してくだされ。話をまとめますんで」
悪い野郎もあったもんで。
松本屋は渡りに舟、とばかりに三両を手文庫から取り出した。
両者から三両ずつ、しめて六両を自分の懐に入れ込んだ狩野屋。悪さの始まりだ。
さて玄益。
その日のうちにお奈美を引き取り、駕籠を出して、長屋に連れてきた。
その日からは、玄益自らが付きっ切りでお奈美の治療にあたった。
その甲斐あってか、お奈美は半年ほどで全快とあいなる。
そのようすを遠巻きに見ていた父親の玄渓。
お奈美の美しくも気立てのいいのを知り得て、二人を夫婦にした。
めでたし、めでたし。
と、いきたいところだが、これでは噺が終わってしまう。もう少しある。
さて。
この「めでたし」を知った、品川宿の狩野屋。
こいつは、すぐに松本屋へ飛び込んでいった。悪さが浮かんだ。
「お奈美が治ったそうですぜ。あいつを返してもらいましょうや。今度は、座敷牢ではなく、座敷へ出せば、まだまだ稼げるタマじゃ、あーりませんか」
狩野屋の申し出を聞いた松本屋義平は、血相変える。
「なあにを言ってる。お奈美は玄益先生が身請けをしたんだ。できるわけがない」
「年季証文はどうなっていますんで」
「え、ああ、あんとき、玄益先生に渡すのを忘れてたな」
「それそれ。ふふふ。証文がこっちにあるんなら、身請けをしたことにゃ、ならねえんで。わたしがうまくまとめますぜ。うまくいったら、十両をいただきやしょうや」
翌日。
狩野屋は、八丁堀の玄益宅に向かった。
「お奈美を引き取らせていただきやしょう」
こう言って、ねじ込んだ。
玄益はびっくり。
「わたしが身請けをしたはずじゃないですか」
「若先生、なにを言ってやがるんで。年季証文は松本屋んとこにあるんだ。出るところへ出りゃあ、あんた、書いた証文が口を利くことになりやすぜ。へへへ」
これでは玄益も声高になる。
双方ともに必死で、甲論乙駁、口論が止まらない。
近くでふだんでないようすを耳にした大家が、間に入ってきた。
「明日、あたしの家に来てくださいな。話をまとめておきますから」
とは、また、骨太な介入で。
いったんは、狩野屋を帰してみたのである。
そして、翌朝。
大家は、すでに一計を案じていた。
大家は、長屋中の欠けた瀬戸物を集めて足の取れかかった膳の上に乗っけて、狩野屋が来るのを待っていた。
狩野屋が来た。
「お奈美は玄益先生が身請けしたはずじゃ、ありませんかい」
大家はここで、玄益の味方につくことを宣言したわけ。
怒ったのは狩野屋だ。
「な、なにを言いやがる」
狩野屋は、体を前に迫り出して、膳を倒して瀬戸物の山を崩してしまった。
あげくのはてには、狩野屋、大家がいつも猫に餌を出してやる皿までぶっ壊してしまった。
大家が怒った。
狩野屋は膳を持って振り上げたので、話し合いは、もつれたまんまとなった。
これはもう、とうとう、お白洲への一本道。
狩野屋が、松本屋義平の名で南町奉行所大岡越前守さまへ、「お恐れながら」と訴え出たのだ。
判決の日。
お奉行は、玄益に申し渡した。
「年季証文が松本屋にあるからは、お奈美を身請けしたことにはならない。身柄は松本屋へ引き渡すのじゃ。よいな」
驚く、玄益ら。
なに、これ。これじゃ、大岡政談にならない。
お奉行はさらに、松本屋にも申し渡した。
「お奈美を治療してもらったのであるから、玄益に薬料、手当て代を支払うように」
その上で、お奉行は玄益にひとこと。
「なみの薬料、手当て代はどれほどじゃ?」
玄益は「そんなの、いりません」と断る。堅物だから。
お奉行はしつこくも「受け取るのじゃ」と言いふくめる。
おっかけて、大家も玄益にけしかける。
「高い値をふっかけなさいよ。ここがお奉行さまの匙加減なんですから」
お奉行が下す。
「試しに算段いたしたところ、薬料は一日に六両、ひと月に百八十両。それに手当て代を一日一両として、月に三十両。お奈美を完治させるのに半年かかったのであるから、お奈美の薬料、手当て代の合計は、千二百六十両である」
これを聞いて、松本屋は腰を抜かした。
「ひ、ひえー」
翌日早々。
狩野屋が大家のもとにやってきて、示談を申し入れた。
勝ち誇ったような言い分の大家。
「あんたは双方から三両ずつ、計六両を懐に入れたんだってね。それはあんたの働きだからいいでしょうよ。だがねえ、膳と瀬戸物を壊したのは間違いなくあんたです。とりわけ猫の皿は高い。しめて千二百六十両いただきやしょう」
狩野屋が「ひ、ひえー、ひえー。ご、ご勘弁ねがいやす」というから、大家が「では、十両で」ということで示談となった。
すごすごと帰る狩野屋。烏が泣いている。
話の顛末をそばで聴いていた大家のかみさんが、大家に話しかける。
「猫の皿は夜店で二文で買ったもんでしょう。それを十両で売るなんて、ずいぶんじゃないですか」
「狩野屋は若先生から三両くすねて、あの始末だ。十両くらいじゃ、まだ足りねえんだよ」
「はいはい。それはそうと、こんなに丸くおさまるというのも、お大岡さまのありがたい、匙加減のおかげですねえ」
「そうだなあ。みんなが、すくわれた(=救われた)」
匙だけに。
【しりたい】
もとは講談ネタ
六代目三遊亭円窓(橋本八郎、1940-2022)が、六代目小金井芦州(岩間虎雄、1926-2003)から習って落語に仕立て上げたそうです。
円窓以外には、入船亭扇辰なども演じています。
匙加減の意味
「匙加減」とは、「薬の調合の加減」の意味。そこから転じて、「手加減」という意味にもなっています。
この噺では、両義がうまく「匙加減」されています。なかなかのもんです。