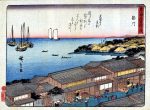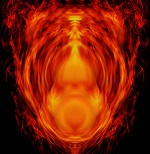【成田小僧】
なりたこぞう
【どんな?】
今は廃れた明治の噺。
マセガキを「成田小僧」といったんだとか。
【あらすじ】
本郷春木町の塗り物屋、十一屋の小僧長松は、口から先に生まれたようなおしゃべり小僧。
父の代参で深川不動に参詣する若だんな江崎清三郎のお供。途中、深川の茶屋松本楼で昼食に。
それも、清三郎が長松の口車に乗ったためだ。
座敷で食事をしていると、芸者が厠に来たのを長松が見つけ大騒ぎ。店の女に聞けば、山谷堀大和屋の小千代。幇間の正孝と花洲といっしょに来ているとのこと。
長松は、幇間ともども呼んでしまう。しめて五十両。
清三郎は
「茶屋へ来たことさえおとっつぁんに知れたらどうしようかと思っているところだのに。私は勘当だ」
とビビるのを、長松は
「長男除きはできやしません。親子の縁の切れなくなったのは、王政ご一新のお上のありがたいところでゲス」
と平気のへいざ。
これが縁で、小千代と清三郎はいい仲に。
後日、吉原の幇間花洲の家に大和屋の女将が訪れた。
小千代が清三郎にばか惚れなのに、近頃、清三郎の姿を見なくなった。
これが続いて、小千代がブラブラ病(恋わずらい)を患う始末。
ついては、花洲に見舞いに来てほしい。
そんな話を、女将は花洲に語って聞かせた。
花洲は、幇間仲間の船八と連れ立ち、山谷堀の大和屋へ。
清三郎との思い出話に花が咲き、小千代の気も紛れる。
ところが、船八は
「若だんなは芸者を連れて逃げたそうです」
と無神経にもしゃべくった。
これを聞いた小千代は顔色を変えて、いきなり外の人力車に乗ってどこかへ走り去った。
花洲、船八、下働きのお梅、大和屋の女将が、次々と車に乗って小千代を追いかける。
話変わって、午後十時過ぎの吾妻橋辺。
清三郎が失踪した日を命日に定め、大だんなが菩提寺の深川浄心寺に長松を連れてお参りに行った帰り道。
清三郎には双子の妹がいた話などを大だんなが長松に語って聞かせているところに、女の身投げを長松が見つけて思い止まらせる。
女は、なんと小千代だった。
話しているうち、小千代こそが大だんなの娘、つまりは清三郎の双子の妹だということが明らかに。
小千代は
「それを聞きましては、なおさら生きてはいられません」
と、ふたたび飛び込みにかかるところ、店の番頭善兵衛が駆けつけた。
若だんなが外務省の役人とサンフランシスコにいる、という手紙が届いたとの知らせ。
一同はほっと安堵、胸をなでおろした。
大だんなが小千代に
「なぜにおまえは貞女の鑑を立てる」
と言えば、小千代が
「元が塗り物屋の鏡台(=兄弟)」
底本:初代三遊亭円遊、「百花園」明治22年5月10日
【しりたい】
深川不動
深川不動は江東区富岡1丁目。成田山新勝寺の東京出張所です。
江戸時代には、日本橋坂本町や蔵前八幡境内に置かれていましたが、明治3年(1870)、現在地の永代寺境内の吉祥院内に移されました。
独立の不動堂が建ったのは明治14年(1881)です。演題の由来はここからです。
成田小僧の意味
当時、ませた子供を「成田小僧」と呼んでいましたが、それがこの噺からきたものかどうか。よくわかりません。
長松のませぶりを成田小僧に見立てて、物語の狂言回しにしようとしたのかもしれません。
本郷の人を深川不動に参詣させて「成田」を取り込んでいるわけです。
物語の重要な転換点では長松がいつも活躍するわけで、狂言回しどころか、やはり主人公なのかもしれません。
円遊の改作
幕末から明治初期にかけて、二代目春風亭柳枝(本名不詳、1822-74)が得意にしていたそうです。
二代目柳枝の芸風は陰気だったそうですから、この噺も元は暗かったことが推しはかられます。
清三郎と小千代がじつは双子の兄妹だったというあたり、幕末に流行した陰惨な因果噺の雰囲気が漂っています。
たとえば、河竹黙阿弥(吉村芳三郎、1816-93)の「三人吉三」なんかが好例ですね。
初代三遊亭円遊(竹内金太郎、1850-1907、鼻の、実は三代目)が、明治22年(1889)5月、23年(1890)11月と、2回に分けて速記を『百花園』に残しています。
陰気な因果噺だったのを、円遊が陽気なこっけい噺に改作しました。
この噺の大きな特徴はここにあります。
二代目柳枝がつくった陰気な噺を、当世人気の初代円遊が陽気な滑稽噺に化粧直しさせてしまった、という。
それでも、今では誰もやらない噺になってしまったのかもしれません。まったくすたれてしまっているのですが。
『落語大会』(松陽堂書店、明治33年12月刊)という落語集に「成田小僧」が「円朝口演」として載っているそうです(筆者未見)。
これを受けてか、角川書店版『三遊亭円朝全集』には「成田小僧」が円朝口演として載っています。
『落語大会』の本文は『百花園』1号(明治22年5月10日)のそれと一致するため、円遊の口演速記を円朝名義で収録したものではないか、というのが佐藤至子氏(東大)の見解です。
この見解のいきさつは、岩波書店版『円朝全集』第13巻に載っています。ちなみに、円遊は円朝の弟子です。
浄心寺
江東区深川平野町2丁目。旧霊厳寺表門前町。
日蓮宗身延山派の名刹で、山号は法苑山。万治元年(1658)開山で、四代将軍家綱の乳母三沢局(浄心院)の菩提を弔うため創建されたものです。
浄心寺門前は、曲亭馬琴(滝沢興邦→解、1767-1848)の出生の地でもあります。馬琴は旗本松平信成家の用人、滝沢興義の五男。曲亭は『漢書』から、馬琴は『十訓抄』から取り、17歳には使っていました。
山谷堀
隅田川から今戸橋を経て、山谷にいたる掘割。
江戸情緒の象徴のような名勝でした。一般には、吉原の入り口付近を指します。
松本楼
富岡八幡宮の鳥居内にあった料亭です。伊勢屋とともに二軒茶屋と称された名店でした。
深川の老舗は、ほかに、平清や小池などがありました。
本郷春木町
文京区本郷3丁目の内。元禄9年(1696)から町地となりました。
町名は、元和年間(1615-24)にこの地に滞在した、伊勢の御師春木太夫に由来します。
明治6年(1873)、同町内に「奥田座」が開場。明治9年(1776)に春木座、35年(1902)に本郷座と改称。
小芝居ながら、明治の名優団菊も出演した由緒ある劇場でしたが、昭和5年(1930)に廃場となりました。
家橘について
「百花園」の「成田小僧」には、長松が、若だんな(清三郎)のことを「家橘に似てる」って絵草紙屋の娘さんが言ってましたよ、とおだてるくだりがあります。
ここで言う「家橘」とは、歌舞伎役者の「市村家橘」のこと。「百花園」が刊行された明治22年(1889)当時なら、九代目市村家橘のことでしょうか。
ややこしいことに、この人は十四代目市村羽左衛門(1848-93、九代目市村家橘)と同一人物。借金返済の事情があって、この時期は初代坂東家橘を名乗っていました。兄は五代目尾上菊五郎(寺島清、1844-1903、音羽屋)で、この人も前名は八代目市村家橘の名乗りでした。
明治17年(1884)に初代坂東家橘を名乗ったのはいいのですが、その後、地方廻りばかりで東京にはしばらく戻ってきていません。
長松の口を通して、清三郎が家橘に似ていると言わせることは、そののち、清三郎が行方知れずになってしまう事態を、聴者に暗示させていたのでしょう。
ちなみに、十代目市村家橘は十五代目市村羽左衛門(市村録太郎、1874-1945)の前名でした。明治10~30年代、「家橘」の八代目、九代目、十代目が続いており、よい名としての通り名だったことがうかがえます。

初代坂東家橘=九代目市村家橘=十四代目市村羽左衛門
明治の料亭
この噺では深川の料理茶屋が出てきますが、幇間の花洲がはやりの店を並べ立てるくだりがあります。いずれも、隅田川沿いの老舗です。
以下に列挙してみましょう。
植半 向島木母寺 境内の植木屋が発端 芋、蜆など 「隅田川花御所染」にも登場
八百松 向島水神森 森鴎外や小山内薫の作品などにも登場
亀清 柳橋 安政元年(1854)、亀屋清兵衛が万八楼を買い取って始めたとか 現存
川長 柳橋
常盤屋
柳光亭 柳橋
倉田屋
柏木 日本橋万町
花清
伊勢源
梅茶
八百善
松源
中村屋
生稲
【語の読みと注】
御師 おんし:伊勢神宮でのみ「おんし」。他社では「おし」。御札を配る人。