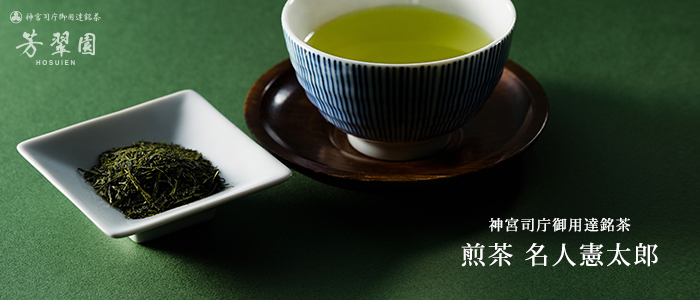【長屋の花見】
ながやのはなみ
見栄張り花見
【どんな噺】
貧乏長屋が花見に出かける。
茶を酒に、こうこを蒲鉾に、沢庵を玉子焼きに、酔ったふりする。
「大家さん、近々長屋にいいことがあります」
「そんなことがわかるのかい」
「酒柱が立ちました」
別題:隅田の花見 貧乏花見(上方)
【あらすじ】
貧乏長屋の一同が、朝そろって大家に呼ばれた。
みんな、てっきり店賃の催促だろうと思って、戦々恐々。
なにしろ、入居してから18年も店賃を一度も入れていない者もいれば、もっと上手はおやじの代から払っていない。
すごいのは
「店賃てな、なんだ」
おそるおそる行ってみると、大家が
「ウチの長屋も貧乏長屋なんぞといわれているが、景気をつけて貧乏神を追っぱらうため、ちょうど春の盛りだし、みんなで上野の山に花見としゃれ込もう」
と言う。
「酒も一升瓶三本用意した」
と聞いて、一同大喜び。
ところが、これが実は番茶を煮だして薄めたもの。
色だけはそっくりで、お茶けでお茶か盛り。
玉子焼きと蒲鉾の重箱も、
「本物を買うぐらいなら、むりしても酒に回す」
と大家が言う通り、中身は沢庵と大根のコウコ。
毛氈も、むしろの代用品。
「まあ、向こうへ行けば、がま口ぐれえ落ちてるかもしれねえ」
と、情なくも、さもしい料簡で出発した。
初めから意気があがらないことはなはだしく、出掛けに骨あげの話をして大家に怒られるなどしながら、ようやく着いた上野の山。
桜は今満開で、大変な人だかり。
毛氈のむしろを思い思いに敷いて、
「ひとつみんな陽気に都々逸でもうなれ」
と大家が言っても、お茶けでは盛り上がらない。
誰ものみたがらず、一口で捨ててしまう。
「熱燗をつけねえ」
「なに、焙じた方が」
「なにを言ってやがる」
「蒲鉾」を食う段になると
「大家さん、あっしゃあこれが好きでね、毎朝味噌汁の実につかいます。胃の悪いときには蒲鉾おろしにしまして」
「なんだ?」
「練馬の方でも、蒲鉾畑が少なくなりまして。うん、こりゃ漬けすぎで、すっぺえ」
玉子焼きは
「尻尾じゃねえとこを、くんねえ」
大家が熊さんに、
「おまえは俳句に凝ってるそうだから、一句どうだ」
と言うと
「花散りて死にとうもなき命かな」
「散る花をナムアミダブツと夕べかな」
「長屋中歯をくいしばる花見かな」
陰気でしかたがない。
月番が大家に、
「おまえはずいぶんめんどう見てるんだから、景気よく酔っぱらえ」
と命令され、ヤケクソで
「酔ったぞッ。オレは酒のんで酔ってるんだぞ。貧乏人だってばかにすんな。借りたもんなんざ、利息をつけて返してやら。くやしいから店賃だけは払わねえ」
「悪い酒だな。どうだ。灘の生一本だ」
「宇治かと思った」
「口あたりはどうだ」
「渋口だ」
酔った気分はどうだと聞くと
「去年、井戸へ落っこちたときと、そっくりだ」
一人が湯のみをじっと見て
「大家さん、近々長屋にいいことがあります」
「そんなことがわかるのかい」
「酒柱が立ちました」
底本:八代目林家正蔵(彦六)
【しりたい】
馬楽の十八番
上方落語「貧乏花見」を、明治37年(1904)ごろ、三代目蝶花楼馬楽(本間弥太郎、1864-1914)が東京に移しました。
三代目馬楽は、奇人でならした薄幸の天才とされています。
明治38年(1905)3月の、日本橋常磐木倶楽部での第4回(第1次)落語研究会に、まだ二つ目ながら「隅田の花見」と題したこの噺を演じました。
これが事実上の東京初演で、大好評を博し、以後、この馬楽の型で多くの演者が手掛けるようになりました。
上方のものは、筋はほぼ同じですが、大家のお声がかりでなく、長屋の有志が自主的に花見に出かけるところが、江戸(東京)と違うところです。
馬楽から小さんへ
馬楽から、弟弟子の四代目柳家小さん(大野菊松、1888-1947)が継承しました。
小さんは、馬楽が出していた女房連をカット、くすぐりも入れて、より笑いの多い楽しめるものに仕上げました。
そのやり方は五代目柳家小さん(小林盛夫、1915-2002)に伝えられ、さらにその門下の十代目柳家小三治(郡山剛蔵、1939-2021)の極めつけへとつながっていきました。
オチは、馬楽のものは「酒柱」と「井戸へ落っこった気分」が逆で、後者で落としています。
このほか、上方のオチを踏襲して、長屋の一同がほかの花見客のドンチャン騒ぎをなれあい喧嘩で妨害し、向こうの取り巻きの幇間が酒樽片手になぐり込んできたのを逆に脅し、幇間がビビって「ちょっと踊らしてもらおうと」「うそォつけ。その酒樽はなんだ?」「酒のお代わりを持ってきました」とする場合もあります。
おなじみのくすぐり
どの演者でも、「長屋中歯を食いしばる」の珍句は入れます。
これは馬楽が考案し、百年も変わっていないくすぐりです。
いかに日本人がプロトタイプに偏執するか、これをもってもわかるというものです。
冒頭の「家賃てえのはなんだ」というのもこの噺ではお決まりですが、こちらは上方で使われていたくすぐりを、そのまま四代目小さんが取り入れたものです。
長屋
表長屋は表通りに面し、二階建てや間口の大きなものが多かったのに対し、裏長屋(裏店)は新道(私道)や横丁、路地に面し、棟割(1棟を間口9尺奥行2間で何棟かに仕切ったもの)になっています。
同じ裏長屋でも、路地に面した外側は鳶頭や手習いの師匠など、ある程度の地位と収入のある者が、木戸内の奥は貧者が住むのが一般的でした。
上野の桜
「花の雲鐘は上野か浅草か」という、芭蕉の有名な句でも知られた上野山は、寛永年間(1624-44)から開けた、江戸でもっとも古く、由緒ある花の名所でした。
寛永寺には将軍家の霊廟があります。
承応3年(1654)以来、皇族の門主の輪王寺宮が住職を務めてきました。
江戸でもっとも「神聖」な地となっていたのです。
ですから、しもじもの乱痴気騒ぎなどはもってのほか。鳴り物は一切禁止でした。いまとは様相が違います。
「山同心」なる連中が、つねに巡回して目を光らせていました。
暮れ六つ(午後6時ごろ)には山門は閉じられる上、花の枝を一本折ってもたちまち御用となるとあって、窮屈極まりないところでした。
そのため、上野の桜はもっぱら文人墨客の愛するものとなっていました。
町人の春の行楽地としては、次第に後から開発された、品川の御殿山、王子の飛鳥山、向島にとって代わられました。
たとえ「代用品」ででも花見でのめや歌えをやらかそうと思えば、この噺にかぎっては、厳密には明治期以後にするか、場所を向島にでも変えなければ、成り立ちません。

名所江戸百景 上野清水堂不忍ノ池 歌川広重 1856年
花見の名所
江戸の花見の名所は、以下のようなところでした。
上野 寛永寺の境内。最上の花見どころ。鳴り物は禁止。
飛鳥山 享保(1716)以降。
向島
御殿山
浅草
隅田川堤
吉原遊郭 夜桜。向島から桜木を運んで移植して散ればまた向島に。
小金井堤
江戸時代は旧暦ですから、花見の時期は2月末から3月末頃です。
現代のような4月の花見はありえません。
【おことわり】「長屋の花見」の別題は「隅田の花見」です。あらすじの底本に用いた『明治大正落語集成』(暉峻康隆、興津要、榎本滋民編、講談社、1980年)の当該頁(第7巻296頁下段)には「隅田の花見」の題名で掲載され、「すだ」とルビが振られています。その根拠はわかりません。ただ、墨田区のHPには、以下のような記載があります。
「すみだ川」の名が登場したのは、西暦835年のこと。当時の政府の公文書に「住田河」と記されています。この「住田」が、どのように読まれていたのかは定かではありませんが、川の三角州に田を作ったという意味で「すだ」と呼ばれていたと考えられています。
和歌山県橋本市の隅田八幡神社も「すだ」と読ませ、川の三角州に田を作ったという同様の由来です。「すだ」は四段活用動詞「すだく」と同根です。意味は「多く集まる」。『明治大正落語集成』はあえて「すだ」としているものと推測できます。「隅田」は古くは「すだ」と読まれていたようで、いつも「すみだ」と読むとはかぎらないのですね。要は「すみだ」も「すだ」も同じで、目くじら立てるものではなかったのです。「隅田の花見」はこれまで、「すだのはなみ」「すみだのはなみ」が混用されてきたのではないでしょうか。われわれは『明治大正落語集成』の編集意図を尊重して、「隅田の花見」の読み方については、できるかぎり「すだのはなみ」「すみだのはなみ」と併記します。